日本の中小企業に擬態し、青い作業服に「ナンセンスマシーン」と呼ばれる摩訶不思議なおもちゃのような製品を携え、国内外でライブや展覧会を行っている芸術ユニット・明和電機。 「アートからマスプロダクトへ」をテーマにオタマトーンなどのヒット商品を生み出したり、子ども向けのワークショップを行ったりするなど、さまざまな活動をしながら、2023年にはデビュー30周年を迎えた。
今回は、そんな明和電機の代表取締役社長・土佐信道に、かねてより交流のある “おねんどお姉さん” ことねんドル岡田ひとみがインタビュー。 土佐の幼少期から明和電機の30年の歩みを振り返ってもらいながら、ものづくりへの姿勢や現代アートシーンへの思いを聞いた。
打楽器とシンセサイザーに見出したアート的な面白さ
岡田:2月に明和電機30周年記念ライブコンサートを行いましたが、大きな節目のライブを終えていかがですか?
土佐:今になってやっと疲れが取れてきました。 僕、周年のイベントってなんかダメなんですよね……。 10周年、20周年のときを振り返っても、まとめに入る感じになってしまうというか。 なので、30周年のライブコンサートは二部制で、一部はダメでもOKという枠にしてまずスベッておこうと思ったんです。 それで、僕一人で楽器をステージ上に運んで組み立てながら演奏したんですけど、演目の1/3を過ぎた時点で終演10分前になってしまって。 どうやっても間に合わないから明和電機の工員たちにステージに出てきてもらってなんとか演目を終えました。 とにかく時間がなくて、ぶっつけ本番だったんですよ。

岡田:20周年ライブのDVDを拝見したのですが、設計図を書きながらライブに挑まれたり、機械が動かないトラブルがあったり、全部計算なのかなと思っていました。
土佐:全然計算じゃないんですよ。
岡田:そうだったんですね。 DVDを見て土佐さんがティンパニがすごく上手なことにも驚きました。 土佐さんは吹奏楽部で打楽器をやっていたそうですが、子どもの頃の楽器演奏の経験は明和電機の活動にも影響していますか?
土佐:すごく影響しています。 最初の音楽体験は、姉が弾いていたエレクトーンですね。 あと、小学3年生の頃に、日本のシンセサイザーのパイオニアである冨田勲さんの『惑星』というアルバムを兄ちゃん(土佐正道。 明和電機会長)と聴いたんです。 ホルストの『惑星』をシンセサイザーだけで再現している作品なんですけど、ただの再現ではなくて、スペースオペラみたいな感じになっていて衝撃でした。 兄ちゃんと「なんなんだこれは!? 全部機械の音か!?」と盛り上がりましたね。
中学1年生のときに吹奏楽部に入って、パーカッションを始めました。 パーカッションは機械の音楽と違ってパッションが大事。 目立ちたがり屋の僕にはぴったりでした。 中学3年生のときに、兄ちゃんがついにシンセサイザーを買ってきて、コンピュータミュージックも作り始めるようになったんです。 そして、大学時代に「打楽器」と「コンピュータミュージック」という僕の二本柱を合わせたら、今の明和電機の原型となる「電気で動く楽器」に行き着きました。

岡田:私は昔から家にオタマトーンがあってよく遊んでいたのですが、オタマトーンの音にもその原体験は影響していますか?
土佐:そうですね。 金管楽器や弦楽器なんかは目指すべき音、つまり、良い音と悪い音があるけれど、打楽器って広く捉えればなんでも打楽器になりますし、叩いた音がいいか悪いかというのは、音楽を演奏するなかでほかの音との関係で決まると思うんです。 例えば、机を叩いて出した音が、ある曲では合わないけれど、ある曲ではすごくしっくりくる。 だから、打楽器は創意工夫の面白さがあってアート的だなと思います。 それに近かったのが、西洋音楽的な音階とはまったく違う音の面白さを電気によって表現するシンセサイザーなんですよね。 幼少期に受けた打楽器とシンセサイザーの洗礼がすべての始まりと言えると思います。
岡田:なるほど。 土佐さんのそういったルーツが活動の基礎になっている点は、30年間ブレることがなかったわけですね。
土佐:そうですね。 「制服」と「ナンセンスマシーンを作る」というコンセプトは変わりません。 でも、自分のなかで抱くテーマは変わっていきます。 20代は魚、30代は花、40代は声、今は箱と、興味のあることが全く違います。 自分の過去の作品がプレッシャーになって「変化しなければならない」と感じることもありますが、歳を取るにつれ見えてくる新しい世界もあるし、自然に変わっていっている気がします。 明和電機は最初からハイアートは目指していなかったんですよね。 A級ではなくB級なんですよ。 だから、Art(アート)ではなく、僕らがやっているのはBrt(バート)。 大衆に向けて売っていきたい、表現したいという思いはずっと変わらないです。


現代美術もプロダクトも「売れる」ものとして完成させるのがプロ
岡田:土佐さんは明和電機でやられていることを「マスプロ芸術」と呼び、今おっしゃってくださったように大衆に売れるようなアートプロダクトを生み出していますよね。 私も子ども向けのねんど教室をやったり、テレビ番組に出たり、商品の監修をしたり、みんなにねんどを身近に感じてほしいと思って活動をする一方で、個展では好き嫌いが分かれるような作品を作ることもあるんです。 いつもはかわいいマカロンやケーキを作るワークショップが人気なのですが、個展でやっているようなことも子どもに教えたいと思い、カビた食パンを作るワークショップを開催したんです。

土佐:いいですねえ!
岡田:でも、やっぱりいつもより人が集まらなくて(笑)。 私は、冷めて固くなってしまったピザとか、しなびた野菜とか、持続不可能な食べ物を作るのが好きなんですけど、まだまだおいしそうで美しいものに需要があるんだなと思いました。

土佐:なるほど、なるほど。 僕、カビた食パンってめちゃくちゃおもしろいと思うんですよ。 カビを使ったアートもいっぱいありますし。 パッケージングの仕方次第かもしれないですね。 僕は青い制服を着ているから興味を持ってもらえることもあると思っていて、岡田さんもアイドルじゃなくてバイキンマンみたいなキャラにするとか……。
岡田:たしかに、入り口を用意するようなパッケージングが必要かもしれないですね。 土佐さんは大衆に受け入れられる作品と、ご自身が作りたいものの間に隔たりがあると感じたときはどうしていますか?
土佐:明和電機も不可解で不条理なものもたくさん作ってきたんですよ。 例えば、魚をテーマにした「魚器(NAKI)*」というシリーズとか。 そういうものを通して、「スマホで調べられることがこの世界のすべてではないんだぞ」ということを見せつけたくなるというか。 僕自身、子どもの頃は、水木しげる先生の作品を見てトイレに行くのも怖くなっちゃったことがありました。 ああいう感覚を体感することって大事だと思うんですよね。

*魚器:自分とはなにか?という命題に対する宗教的、科学的、芸術的なアプローチを、魚というモチーフで装置化したシリーズ。 1992年からスタートし、「グラフィッシュ(死の瞬間を記録した、時間軸のある魚拓)」や「ハンマーヘッド(パンチカードで電磁石を動かし、ホルマリン漬けの鯉の尻尾を動かす装置)」など26 個の製品を制作した。
岡田:子ども向けのワークショップではそういったことを伝えているんですか?
土佐:僕らは「ものづくりのワークショップ」と「発想のワークショップ」の2種類をやっているのですが、前者のときはすごくシンプルに「片付けながら作れ」とか「怪我をしないでものづくりをする方法があるんだ」という、至極まっとうなことを教えています。 発想のワークショップのほうは、「脳みそはもともとおかしなことを考えるようにできている」ということを伝えていて。 脳みその普段使っていない部分をひらいていくために、「ナンセンス」を実際に見せ、体験してもらっています。
岡田:アーティストも、脳みそがもともと考えるおかしなことを結晶させてものづくりをしていると思うんです。 そして、それにはすごく時間やエネルギーがかかる。 アートを生業とすることの難しさはそこにあるのかなと思います。
土佐:アートで「食えて」いるプロフェッショナルの現代美術作家って、アートで「商品」を作れる人だと思うんです。 一線で活躍している現代美術作家が作る作品は、商品として見事に完成している側面が必ずある。 コンセプト設計から作品の仕立て、パッケージングまでを戦略的にやっていて、ちゃんと売れる要素がある作品を作っている人たちなんですよ。 作品を売れるところまで持っていくのがプロだと思います。 そこにおいては、現代美術もプロダクトも、僕のマスプロダクトも変わらないと思います。 人の欲望や感情を掻き立てるものでないといけない。
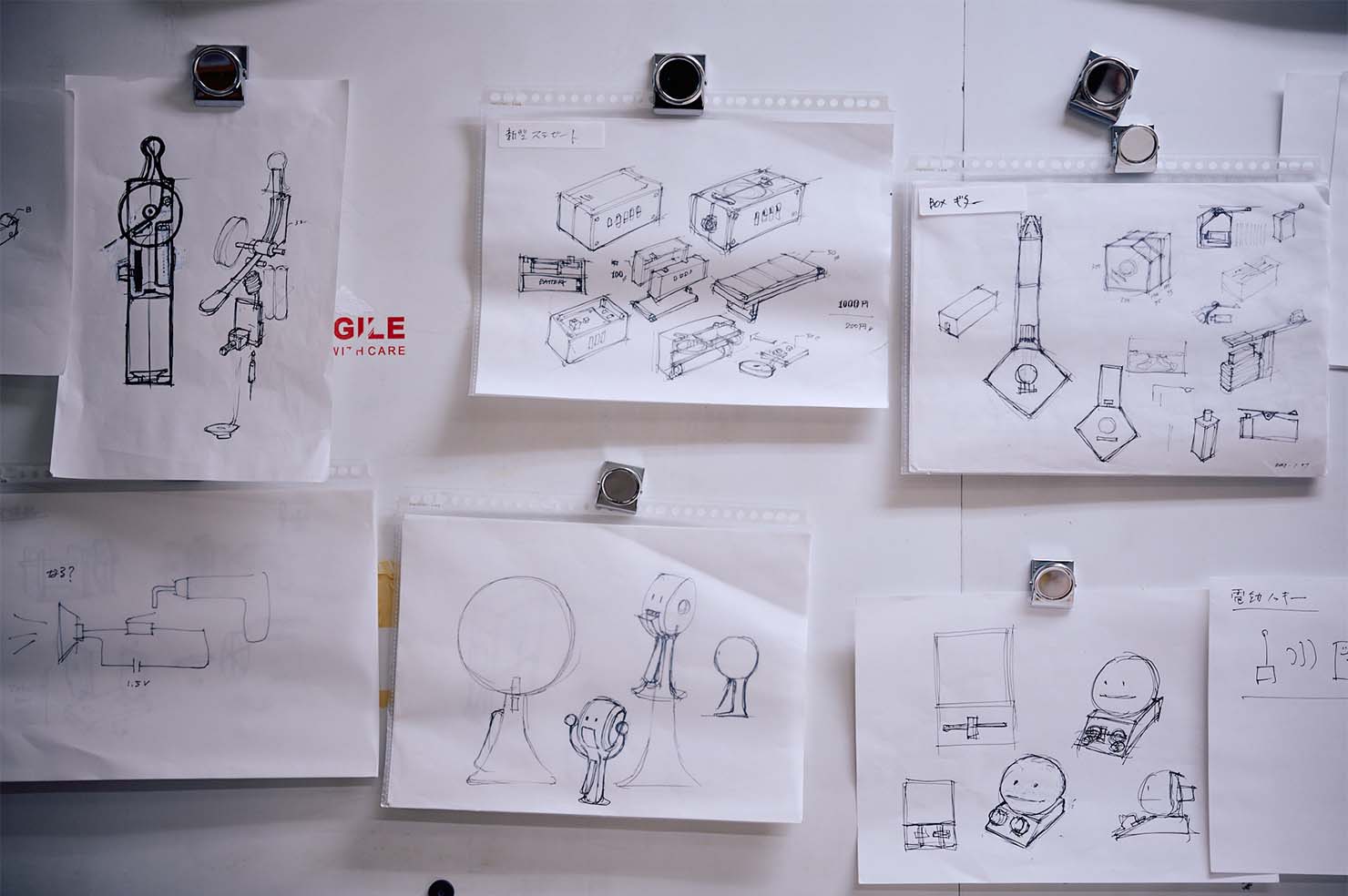
岡田:明和電機がマスプロダクトの方向へ進んでいったのはなぜだったんでしょうか?
土佐:現代アートシーンは少し金融的になってきていることが気になっていて。 高い価値を生むというのはつまり、それまでの世界になかったものですから、現代美術が投機・投資の対象となって金融的な価値を持つのは仕方のないことだと思います。 一方で、金融的価値とアートそのものの価値は違うと思うんです。 だから僕たちは「アートからマスプロへ」ということを掲げてマスプロダクトを作る。 つまり、100個作った作品が100人に買われるほうが、作品そのものの価値を評価してもらうという意味でしっくりくるなと思ったんです。
ターゲットは小学3年生のころの自分
岡田:それをまさに体現しているのがオタマトーンだと思うのですが、オタマトーンのようなヒット商品に必要なものって何だと思いますか?

土佐:オタマトーンの出発点は「声とは何か?」というテーマでした。 とにかく自分が面白いと思うものを探求して、作っていてすごく楽しかった。 自分が欲しいと思えるおもちゃができたし、絶対的な自信がありました。 なので、多くの人がオタマトーンを面白がってくれたのも、ある意味当然と思えました。 ものづくりにおいて、アート的なアプローチが有効な部分は、作り手自身が面白いと思うものを徹底的に作り込むところにあると思います。 デザインはニーズに合わせていくものですが、アートの絶対軸は自己表現。 そういう意味で、明和電機はデザインではなくアート、もっと言うとBrt(バート)なんですよ。 洗練されすぎてもダメだし、日常に入り込むようなB級感のさじ加減がいちばん難しいところかもしれません。
岡田:土佐さんはいつもどんなターゲット像を思い浮かべて制作しているんですか?
土佐:小学生のときの自分ですね。 冨田勲にハマったときの小3の自分、ミクロマンの箱を開けて狂喜乱舞した自分を思い出して、「オタマトーンはそうなり得ているのだろうか?」みたいなことは考えますね。 当時の自分が「ギャー!! きたー!!」となるようなものを作らないといけないなと思っています。

岡田:なるほど……!そんな土佐さんが、もしオーディオテクニカの社員だったらどんな製品を作りますか?
土佐:まずは倉庫を見てこれまでにオーディオテクニカが何を作ってきたのかを調べて、昔の技術を発掘し、今の技術とコンバインして作りたいですね。 例えばドローンが次世代のテクノロジーのようになったのは、通信の速度や質が上がったからで、モーターなどの駆動に関する部分の技術は結構昔ながらのものだったりするんです。 そういう、新旧のテクノロジーの組み合わせからプロダクトを作ってみたいですね。
岡田:今の技術というとAIの成長も目覚ましいですよね。
土佐:ちょうど先日、シャッターゴルフというAIに考えてもらった架空のスポーツをテーマにしたインスタレーションをやりました。 AIにクリエーションを補助してもらったわけですが、最終的には全体的に手直しをする必要がありました。 人間って、やっぱり人間が作り出したものを知覚するようにできているんだと思うんですよ。 フランシス・ベーコンの絵が心地いいのは、キモかわいいに近い「キモ心地いい」なんですよね。 AIも似たような「キモさ」のある表現を作り出すことがあるけれど、それは単なるバグ。 人間が作ってきたものを学習して描いてはいるけど、人間のことを考えずに生成されているから、違和感があって気持ち悪いものになる。 僕はそれを「苦味」と呼んでいるのですが、AIが作ったものは、最終的にはその苦味を取る作業を人間がしなければいけないと思っています。
岡田:私もすごくアナログな作品を作っていますから、とても共感します。 でも、例えばメタバース空間で明和電機のナンセンスマシーンが使える、みたいな構想もありえるのかなと思ったのですがいかがでしょう?
土佐:僕は小さい頃は絵描きになりたかったけど、そこから離れて機械にいったのは、コンテンツじゃなくツールがつくりたかったからだと思っているんです。 仮想空間にあるものはすべてがコンテンツですから、あまり興味がないんです。 物理の世界で楽器を作っていきたいと思っています。
岡田:なるほど。 明和電機はこれからどんな活動をしていきますか?
土佐:打倒オタマトーンです。 流行は時代で変わっていきますが、オタマトーンはむにゅっと潰して音を出す体感的な面白さでウケているし、人間が本質的に面白いと思うことはそうそう変わらないと思うんです。 おもちゃが何をもっておもちゃであるかというと、「面白い」しかないと思うんですよね。 面白ければ高級車であろうが野菜であろうがおもちゃになる。 オタマトーンとは別の、人間の本質的な面白さに触れるものを作っていきたいです。

明和電機
土佐信道プロデュースによる芸術ユニット。 青い作業服を着用し作品を「製品」、ライブを「製品デモンストレーション」と呼ぶなど、日本の高度経済成長を支えた中小企業のスタイルで、様々なナンセンスマシーンを開発し、ライブや展覧会など、国内のみならず広く海外でも発表。 音符の形の電子楽器「オタマトーン」などの商品開発も行う。 オタマトーンは累計販売数200万本を超えるヒット商品(2023年8月現在)。
2016年1月には中国上海の美術館McaMで、初の大規模展覧会を成功させた。 2019年3月には秋葉原「東京ラジオデパート」にて明和電機初の公式ショップ「明和電機秋葉原店」をオープン。 2021年は豊川(愛知)で個展を開催、北京(中国)で全リモートで展示設営を行った「超常识创造力工场•明和电机学艺展」を開催した。
2023年にはデビュー30周年を迎えた。 同年9月呉市立美術館、12月札幌の森美術館で個展を開催した。
ねんドル岡田ひとみ
親子ねんど教室、書籍の執筆、原型デザインなどを行い、ねんどの持つ可能性を探る。 3歳から参加できるねんど教室は年間 1万人以上、海外では五大陸30都市以上で開催。 現在、NHK Eテレ『ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!』ではおねんどお姉さん“ひとみ”とその姉“コネル”として出演中。
Photos:Manabu Morooka
Words:Aiko Iijima(sou)
Edit:Kunihiro Miki


