2018年、ロンドンを皮切りにスタートしたオルタナティブな音楽イベント「MODE」。 同イベントはコロナ禍を経た2023年、東京を新たな拠点に復活を果たし、その年末にはGOLDWINとSpiberの協働によって誕生した新たな共同体でありコレクションでもある「REGENERATIVE CIRCLE」のサポートの元、リキ・ヒダカ(Riki Hidaka)、タシ・ワダ(Tashi Wada)とジュリア・ホルター(Julia Holter)のデュオ、ローレル・ヘイロー(Laurel Halo)がライブを行うスピンオフイベントが開催されました。
ヴェニューは新宿区に位置する、美しいコンクリートシェル構造の礼拝堂を有する「ウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会」。 教会音楽とはどういったものかを振り返り、いま、都会の一角にある教会でMODEのような特殊なイベントが行われた理由を、編集を核に色々な事業に取り組んでいるWATARIGARASUのディレクター、大隅祐輔さんが考察しました。
教会音楽において重要なのは演奏する者、聴く者、それぞれの敬虔さと共感
ポストクラシカルの代表的な作家であるマックス・リヒター(Max Richter)による、「眠り」をテーマとした『SLEEP』という8時間以上に及ぶ作品がある。 LAのグランドパーク、アントワープの礼拝堂などで真夜中に行われた同作の上演映像に、リヒターと妻の回想を織り交ぜた映画『SLEEP マックス・リヒターからの招待状』の中でリヒター自身が語った一節がある。
生活は日々 慌ただしくなる
“昔より穏やかだ”と言う人はいない
あらゆる物事が休まず前進する
それが現代の生活だ
加速し続ける企業には好都合かもしれないが
個人でもそうだろうか?分からない
だから無言の抗議の意味を込め
この作品を作った
音楽、とりわけ教会で奏でられてきたものは、この言葉のような慌ただしい世俗から距離を置き、急速に流れる前進から外れ、自己を見つめ直し、他者を憐れむための一時を提供してきた。 本題に入る前に、群馬県立女子大学等で講師を務めている清水康宏氏の東京大学在学時の論文をかい摘みながら教会音楽に関する前置きを記してみたい。

かつての教会音楽には絶対的に相応しいとされているものがあり、それ以外は排他される傾向にあった。 議論が活発化したのは19世紀。 産業革命が起こり、近代化が世界的に広がっていく前夜である。 この時期は、ヨーロッパで様々な芸術が花開いたルネサンス期に当たり、例に漏れず、西洋音楽もより技巧的になったり、シャンソンやオペラといったポピュラー音楽が誕生するなど、作曲家が独自性を追求するのと同時に多様になっていった。
ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンといった大作家たちは新しい教会音楽、交響曲の創造を試みたのだが、純粋性の高い無伴奏の聖歌を重んじてきた「模範」の復興派から「大規模過ぎる」などと批判を受けてしまう。 それに対して、過去をただ省みるのではなく、訪れた新時代に相応しい礼拝観を考えたのが当時の批評家、アルベルト・ゲレオン・シュタイン(Albert Gereon Stein)である。
シュタインが教会音楽において重要と考えていたのは、古い様式への理想を語ることよりも、礼拝に参加する人の敬虔(=深く敬って態度を慎む様)な気持ちとその教化という本質だった。 上記論文によれば、シュタインは派手と見なされたベートーヴェンの宗教音楽をこう評したという。 「あらゆる啓示、宗教の狭い境界線をはるかに超え出て、それ自体が啓示、最も深い信仰、和解への最も熱烈なあこがれ」。 作曲家の心が感じたもの、感情によって構成された自由な音楽こそが、聴き手との共感をもたらすとしたのだ。
教会音楽が宗教の「境界線」、言語を超えて多くの人に開かれるには、この話から約1世紀の時を待たなければならなかったようだが、音楽による自由と解放を求めるための懐疑、変化の受容がなければ、先のリヒターのアプローチ、そしてこれから触れていく本題のようなことは起きなかったかもしれない。 重要なのは演奏する者、聴く者、それぞれの素直な敬虔さと言葉の説明では足らない深い共感なのだ。
混沌とした世の中に対する鎮魂のような幕開け

「本題」が行われた場所は東京・新宿区の大久保、百人町。 比較的小さな駅舎を出ると、高架下から飲食店などが鮨詰めのように並び、狭い歩道には夜間でも多くの人が行き交う。 東京都庁をはじめとする高層ビルや高級ホテルがそびえ立つ東京のコアのひとつ、新宿の端っこにあるこの雑踏には、教会が比較的多く存在している。 その中でもとりわけ大きく、約22mもの天井高の礼拝堂を有する「ウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会」が「本題」である音楽イベント「MODE」のスピンオフ「MODE AT YODOBASHI CHURCH Supported by REGENERATIVE CIRCLE」のベニューだった。
MODEは、音楽レーベル兼プロダクション「33-33(サーティースリー・サーティースリー)」主宰、昨年逝去してしまった坂本龍一キュレーションのもと、2018年にロンドンで初開催され、2019年の第2回目、コロナ禍を経て、2023年5、6月にキュレトリアル・コレクティブ「BLISS(ブリス)」との共同企画によって東京で復活した。 (残念ながら筆者が観られなかった)復活時は数日間に渡って複数箇所で行われ、メルツバウ(MERZBOW)やスティーヴン・オマリー(Stephen O’mally)といったノイズ/ドローンミュージック界のキングや、ひとつひとつの説明は避けさせて頂くが、イーライ・ケスラー(Eli Keszler)、ベアトリス・ディロン(Beatrice Dillon)、ルーシー・レイルトン(Lucy Railton)、YPY、FUJI|||||||||||TA、カリ・マローン(Kali Malone)などのニューオルタナティブ、ニュープログレッシヴ(あるいは、それこそポスト・ポストクラシカル)と言うべきか、とにかく枠には収まり切らない、国内外の新世代かつ急進的なアーティストが名を連ね、2019年に亡くなった名雅楽師、芝祐靖の作品を雅楽グループ、伶楽舎が演奏し、さらなる異形の華を添える、MODEのドメイン「mode.exchange」に用いられている「交換」をつまびらかにする横断的なラインナップだった。
MODE開催に関するニュースを見ると、「実験音楽」という言葉が枕詞のように頻繁に使われていて、少しばかり目についてしまった。 確かに、最先端の技術的プレゼンテーションも兼ね備える他の音楽フェスティバルとは相反するオーセンティックな響きとその変容(ルーシー・レイルトンはチェリストでFUJI|||||||||||TA、カリ・マローンはパイプオルガンをメイン楽器とし、YPYは和太鼓集団の鼓童とのコラボレーションでも知られている)にフォーカスしたイベントを形容するのに、電子音楽という「ジャンル」ではなく実験音楽という「曖昧な括り」が端的な言葉であることは分かる。 しかし、そういった紋切り型の片付け方をしてしまって良いのだろうか、というのがイベント鑑賞後の素直な感想だ。
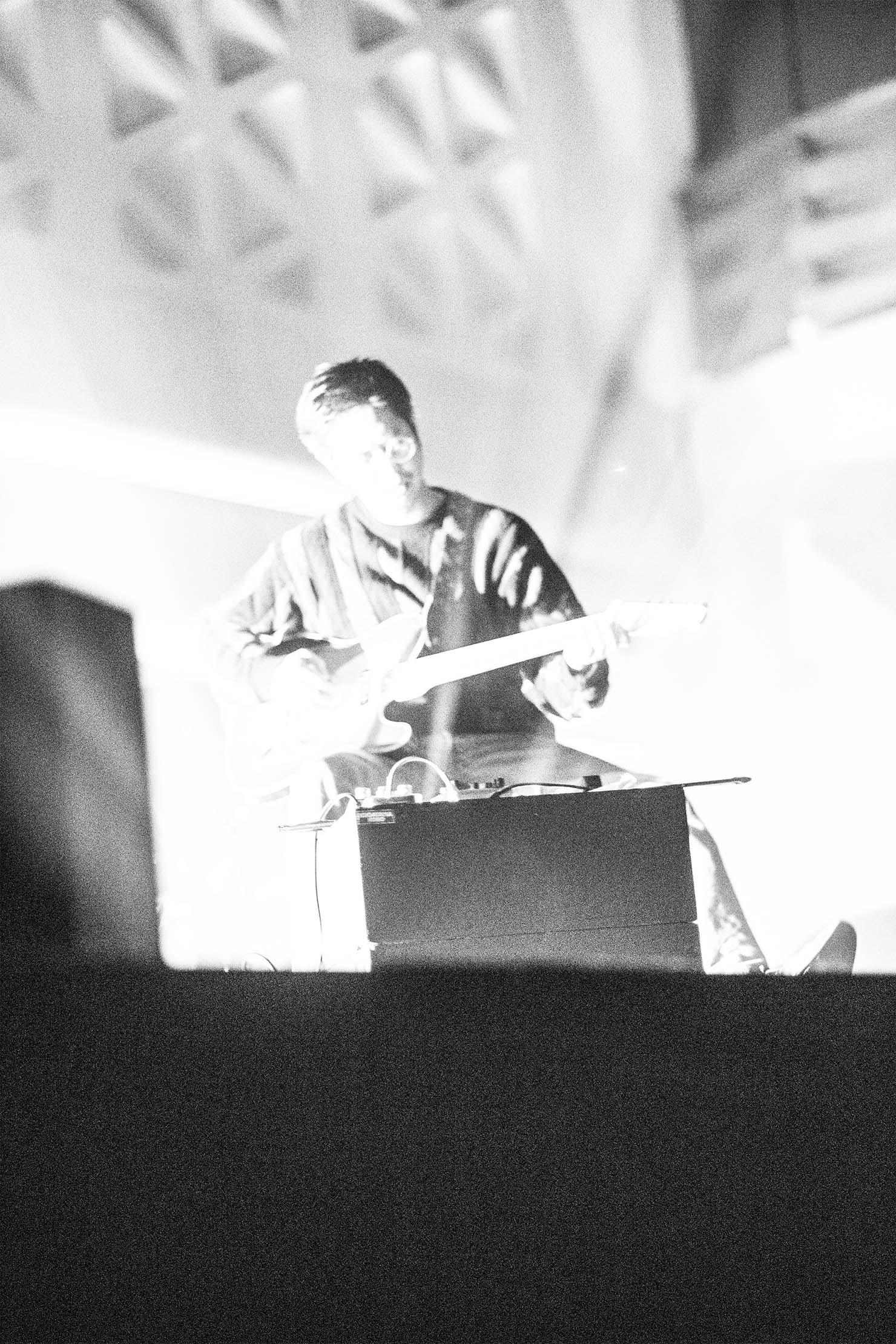


MODEスピンオフ版の出演は、5月のMODEにも参加した、ele-king誌が太鼓判を押し過去に「生粋のボヘミアン」と評したほどに神出鬼没なギタリスト、リキ・ヒダカ。 フルクサスに参画し、ラ・モンテ・ヤング(La Monte Young)らと共にドローンミュージックの開祖的存在と言われるヨシ・ワダ(Yoshi Wada、本名・和田義正)の意志を受け継ぐ息子、タシ・ワダと時にコラール(=讃美歌)と呼ぶべきだろう流麗な歌唱をポップミュージックに織り交ぜるコンポーザー、ジュリア・ホルターのデュオ。 様々な音色、自身の歌声がタペストリーのように出入りし、そこにビートが疾走感と規律を与えながらも怪しげに進んでいくアルバム『Quarantine』で衝撃的なデビューを飾り、クラブを主戦場としているかと思いきや、4枚目のアルバム(正確にはミニLPだが)では畳み掛けるピアノによるミニマルミュージック、シンフォニーに大きく舵を切り、リスナーへの良い意味での裏切りを続けるローレル・ヘイロー。 この3組だった。


リキのかったるそうなお辞儀から演目はスタートした。 何かを炙っているかのようなチリチリと小刻みに鳴るノイズに、ギターの弦を半永久的に振動させるE-BOW、ヴァイオリンの弓が放つ穏やかなドローンサウンドが段々と音の層を作り出し、礼拝堂の空間を埋め尽くす。 そこに独創性や難解さは(何なら実験性も)なく、おそらく思い思いに重ねられていったサウンドは、まっさらな地平を描くようにシンプルで、ポルトガルのリスボンを拠点とするギタリストでサウンドアーティストであるラファエル・トラル(Rafael Toral)の初期作を思わせるほどに清々しい。 混沌とした世の中に対する鎮魂のような幕開けだ。
急速に流れる前進から外れ、自己を見つめ直し、他者を憐れむための一時としての音楽


そのバトンを手渡されたタシ・ワダ、ジュリア・ホルターは煌びやかなシンセサイザーによるドローンの二重奏を奏で、そこにジュリアの優しげなハミングが加わる。 一旦閉じられた世界、聖域が次第にはなやいでいく感覚。 陶酔感を覚えながら礼拝堂の高い天井を眺めていると、バグパイプの音がどこからともなく流れてくる。 タシがバグパイプを吹きながら、観客が座る椅子の間をゆっくりと歩き回っているのだ。 父、ヨシ・ワダもバグパイプの名手だったことで知られているが、タシのこのパフォーマンスを観て、父の後継というよりも先に思い起こしたのはドイツの寓話「ハーメルンの笛吹き」並びに、その話をベースとしたネビル・シュートによる1942年の小説『パイド・パイパー 自由への越境』である。

前者に関しては未だに善か悪かの議論がなされており、真実が謎のままなのだが、とある笛吹きが町の広場で笛を吹き、人を集め、資源や食料が豊富にある新天地に子供をはじめとする市民を連れ立った、笛吹きは移民のリーダーだったという説がある。 後者は戦火を逃れるために、とある老人が偶然出会った子供たちと共に歩きながら、安全地帯である故郷を目指す冒険物語。 それらのエピソードを思い起こし、重ね合わせ、タシが歩きながら鳴らした笛の音色は、「ここ」に現れた安全な「聖域」深くへの誘いだと思ったのだ。

これらの伏線が引かれた後のラスト、ローレル・ヘイローのライブは大いなる「裏切り」と驚きをもたらし話題となった昨年リリースされたアルバム『Atlas』のアイデアがもとにはなっている。 大雑把に言えば、先で少しだけ触れた本作のコラボレーターであるルーシー・レイルトンなどによるストリングスとサウンドスケープとピアノの麗しい協奏曲の連なりなのだが、徹頭徹尾、非常に美しくまとめ上げられているアルバムとは異なり、ライブでは大胆な対比構造になっていた。


ライブ中、思いつく限り打っていたメモを見返すと「チェンバロ、オルガン、バイク、モーター、サイレン、、、」と書かれていて、都会の喧騒を想起させるこれらの音が圧縮されたバックトラックがけたたましく鳴る中でローレルはひとり、祈るようにピアノと向き合い、おそらく即興で弾き続ける。 こういった構造の場合、大抵はバックトラックと演奏が次第にミックスされていくものなのだが、トラックとピアノの独奏の波長は基本的に噛み合わない。 一瞬、合ったかな、と思っても、どんどんズレていく。 まるで教会の内と外を表しているかのように。 あんなにスリリングな演奏は、未だかつて観たことがなかった。

リキ、タシ+ジュリアが教会という「聖域」のひとつの単位の新たな物語を生み、ローレルが視野を大きく広げ、都会〜雑踏〜聖域全体の「いま」、つまり「Atlas(=地図)」を表現し、導かれていった敬虔な気持ちから大幅なズレがある外にも意識を向かわせる。
以上は筆者の主観的な見立てではあるので、この構成が意図的だったのかどうかは分からないが、素晴らしいキュレーションだった。 まさしく、「急速に流れる前進から外れ、自己を見つめ直し、他者を憐れむための一時」だったように思う。
『Atlas』がリリースされた際に行われた、アメリカのラジオ放送局「npr」のローレルへのショートインタビューでローレルは「(『Atlas』は)聴く人を回復させられるピースフルなものが作れたら美しいと思ってできた作品」と語っていた。 晩年まで平和を求め、作品を作り、活動していた坂本龍一への哀悼の意をウェブサイトに残し続けているMODEも、その意志と態度を受け継ごうとしているに違いない。 そして何よりも新しい、否、いまにこそ相応しい教会音楽の在り方を提示したことを評価すべきだと思う。
Photos:Yuichiro Noda, courtesy of MODE
Words:Yusuke Osumi(WATARIGARASU)


