集中したいとき、リラックスしたいとき、元気になりたいとき、泣きたいとき……。日常に欠かせない音楽は、なぜ私たちの心を魅了し、強く揺さぶるのか。
脳科学者の養老孟司氏と音楽家の久石譲氏の対談を収録した『脳は耳で感動する』(実業之日本社刊)は、言葉にできない情動をロジカルに紐解いた名著だ。脳科学の視点から音楽の魅力に迫る本の内容を、一部抜粋・再構成してお届けする。
脳の邪魔をしないのが名曲?
久石:養老さんは、音楽はよく聴かれるんですか?
養老:聴きますよ。ただ、あんまり暇がなくてね、コンサートホールにはもうずいぶん行ってないですけど。もっぱら家でCDかけたり、iPod使ったりしてます。
久石:iPod使われるんですか?
養老:外では使いませんけどね。外にいる時にイヤホンで耳を塞いで歩いているのは、目をつぶって歩いているようなものじゃないですか、傍若無人だって刺されるかもしれない(笑)。うちの中で、捕ってきた虫の研究をしたり何か考えたりする作業をしている時に聴いているんです。
久石:聴かれるのはクラシックですか?
養老:そうですね。基本的に「ながら聴き」なので、この曲が好きとかなんとかで選ぶんじゃなくて、仕事の邪魔にならないものを選んでいます。
久石:モーツァルトとか?
養老:そうですね、あれは邪魔になりませんね。歌だったらタンゴとか。スペイン語だと言葉がわからないから、「ああ、いい声だなあ」と感じるだけだから。
久石:歌詞が入ってこないからノイズにならないわけですね?
養老:本当に集中している時は聞こえてないんですよ。それでも思考の途中で、ふっと気持ちがよそへ行く、そういう時に聞こえてくる音楽が気持ちのいいものだといいんです。「聴きなさい!」とばかりに何かを強く訴えかけてくるようなものだと、ちょっと具合悪い(笑)。
久石:宮崎駿さんも絵コンテ切っている時など、絶えず音楽をかけているらしいんです。だけど、集中しては聴いてないんだよ、とおっしゃる(笑)。
養老:それは聴いてないというより、意識に入ってないんですよ、おそらく。意識では気がついてないだけ、何か影響は受けているはずなんです。
久石:脳の働きを邪魔しない音楽というのは、僕も非常によくわかります。作曲家として、ある種、目指しているところでもありますから。今回はそんな話もできればいいなあと思っています。
映像より音楽が先に脳に飛び込む
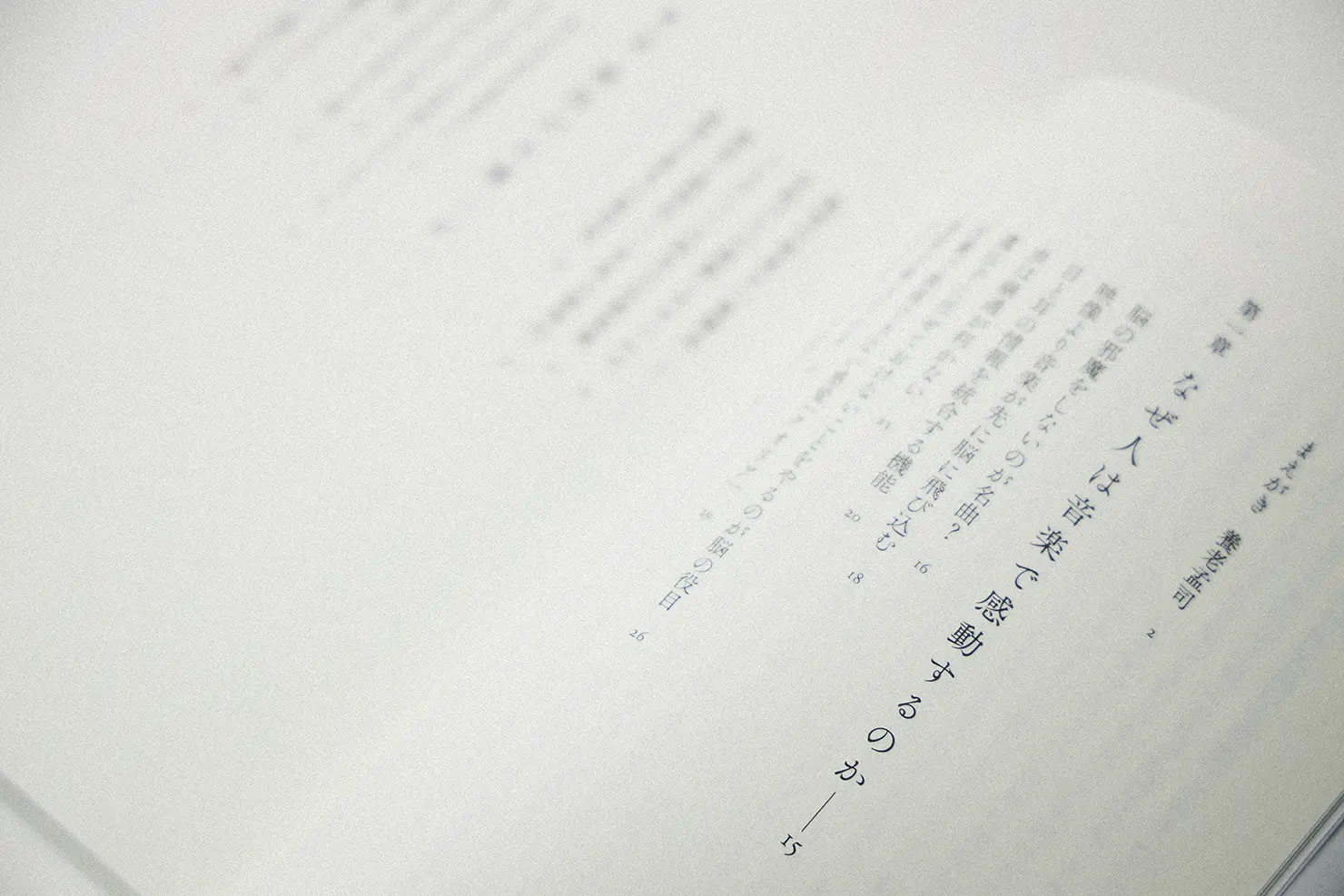
久石:僕は映画音楽を続けていて、素朴な疑問として感じてきたことがあるんです。それは映像と音楽が人の脳に入ってくるスピードです。
ご存知のように、映画というのは一秒に24コマの映像が流れます。映画音楽というのは、そのコマレベルまで合わせていく作業になるわけです。ところが、厳密に映像に合わせて音楽をつけると、間違いなく音楽の方が早く感じるんですよ。ぴったり合わせると、映像より先に音が聞こえてくるという現象が起きる。
僕は経験則で、3コマか4コマ、場合によっては5コマ、音楽を遅らせたりしてきました。そうすると、映像と音楽がちょうど合う、違和感なくシンクロするんです。
普通に考えたら、映像は光ですから、音速より速いですよね。それなのに音の方が早く感じられる。これがどういうメカニズムなのか不思議に思ってきたんです。
養老:それは意識の研究者が指摘しています。視覚と聴覚は処理時間がズレる。何の問題かというと、おそらくシナプスの数です。
意識がどういう形で発生するかわかりませんけど、自分がこういうことを見ているというのと、聞こえてくるのと、脳の神経細胞が伝達して意識が発生するまでの時間が、視覚系と聴覚系とでは違う。だからズレているわけです。
ただ、僕は根本的にはそれが当然だと思っています。というのは、目から入ってくるものと、耳から入ってくるものを合わせて捉えようなんてことをするのは、人間だけなんです、たぶん。本来、別々なものなんですよ。
久石:なるほど。
養老:その本来は別のものをつかまえる機能を結びつけて、両方一緒にしようとしたのが人間の人間らしいところです。
普通は、それを意識しなくなっているんです。久石さんの音楽と『崖の上のポニョ』のシーンがうまい具合に合体しているのを、不思議だと思っている人はいない(笑)。だけど、久石さん自身は、コンマ何秒という非常に細かいレベルで仕事をされているから、ズレがわかる。そういう状況ですね。
逆にいえば、その音と映像のズレを利用することで、非常に妙なシーンとか奇妙なズレ感覚の映画がつくれるんじゃないですかね。
久石:ああ、それはありますね。
目と耳の情報を統合する機能

養老:野外に出てみたら、聞こえる音と目に見える景色は別ものだということが、よくわかります。音がするから、「ああ、川があるんだな」とわかる。
久石:あっ、そうだ、音が先ですね。
養老:しかも小川のせせらぎというのは、森林のさまざまな木なんかと共鳴することで強く聞こえてくる。しかしそんなもの、見えるはずがない。外から聞こえてくる音と、我々が見ている風景は一致していない。当たり前のことなんです。
スリランカで地震があった時、津波がまだ来ていないうちからゾウが一斉に内陸へ逃げたという話がある。耳が「危ないよ」と知らせているんです。それを見て人間も一緒に逃げればいいんだけど、ぐずぐずしてしまう。津波を目で確認してからあわてて逃げようとしたって、そりゃあ間に合いません。動物は人間みたいに複雑に考える能力を持っていない。だから自然なんです。
久石:人間の脳はなぜそういう能力、目と耳から入ってくるものを一緒にするような機能を持ったんでしょう?
養老:おそらく、他の動物は脳みそが小さすぎてその必要がないんです。人間は脳が進化して意識が発生してきた。そうなると、目から入ってきた情報を処理してわかることと、耳から入ってきた情報を処理してわかること、どっちのいうことをきいたらいいのかわからなくなる。
つまり、目と耳から違うことが入ってくるからこそ、どちらも「同じ自分だよ」という機能を同時に発達させないといけなかったんだと思います。でないと、完全に人格分裂しちゃいますから。
脳みそが大きくなってきて、目に直属するのでも、耳に直属する分野でもない、いってみれば余分な分野ができてきた。人間の場合、そこが非常に大きくなった。簡単にいえば、それがいわゆる「連合野」です。
そして、目からの情報と耳からの情報、二つの異質な感覚を連合させたところにつくられたのが「言葉」。人間は「言葉」を持つことで、世界を「同じ」にしてしまえたんです。
言葉で表現できない感覚「クオリア」
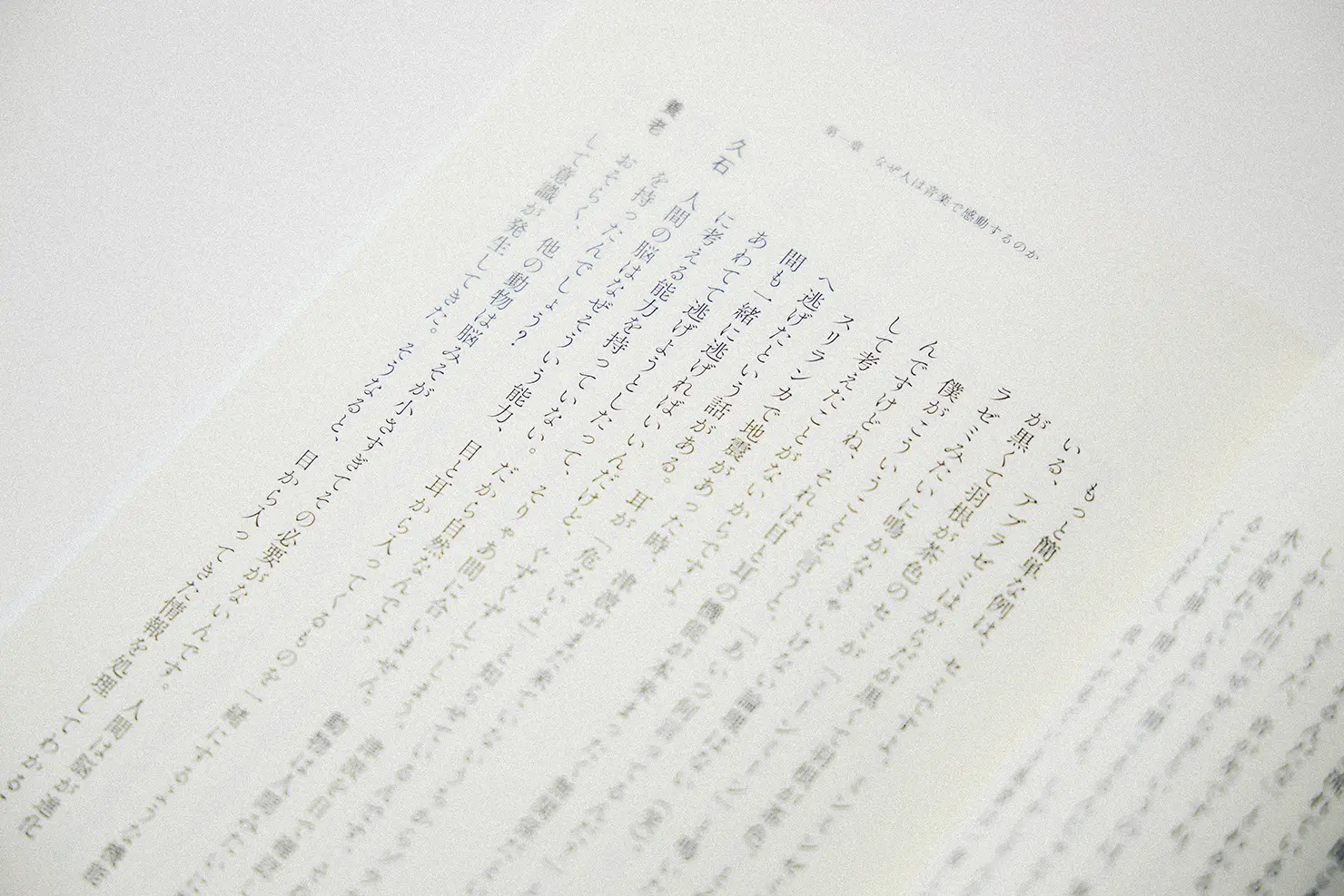
養老:今の人の悪いクセは、何でも「言葉」で説明できて、理解できると思っているところだと僕は思っています。だから意識的に言葉で説明することを求める。
学生がよく「先生、説明してください」と言います。僕はそれを言われた途端に機嫌が悪くなる(笑)。医学部で、男子が多いでしょう。「説明したら、陣痛がわかるか?」と言うんです。どういうふうに痛いか説明されたら理解できるかって、そんなのわかりっこありませんよ。
久石:体験したことのある人でなければ絶対わかりませんからね。
養老:それを、哲学では「クオリア」というんです。茂木健一郎君が「クオリア」ということをよく言っていますが、言葉ですくいきれなくて落ちていく部分というのが必ずあるわけです。
いろんなふうに落ちるんですけど、たとえば我々は、ものを名前で呼びます。自然のものを、たとえばリンゴならリンゴと言う。だけどリンゴにもいろいろな種類がある。黄色いのも青いのも赤いのも、甘いのも酸っぱいのも、大きいのも小さいのも、木になっているのも、八百屋で売っているのも、腐って落っこちているのもさまざまです。
それが言葉としては「リンゴ」の一語で言い表せます。一見便利なようですが、「リンゴ」という言葉を使った瞬間に、そのリンゴの持っているいろんなものが落ちる。そういうふうに言葉で表現しようとすると必ず落ちていく、絶対に比べようがないものを、哲学では「クオリア」という。
ところが、今は現実よりも言葉が優先するんですね。そして言葉にならないことは、「ないこと」になってしまうんです。そうした中で、かろうじて絵とか音楽とか、いわゆる芸術といわれるものが、言葉にならないものとして踏みとどまっている。
言葉で説明できるなら、音楽は要らない
養老:それからはっきりしているのは、芸術が教育の中からどんどんなくなってきている。教育といえば、試験に通ることだと思うようになっている。昔は「情操教育」といいましたけど、もはや情操的なものを育てることを教育が含んでいるとは、みんな思っていないんじゃないかなあ、それこそ先生も、親も。
久石:ええ、知識として形にならない、覚えてアウトプットできないものは価値がないという感じになっていますからね。音楽にしても、ベートーヴェンの何と何と何の曲を知っているというのは、単に記号化された記憶でしかない。
そういうことをたくさん知っていて答案用紙を埋めることができたとしても、それは音楽を知っている、味わっていることとはまったく別ものです。
養老:音楽から影響を受けることができる能力なんか測ってませんものね。それが感性とか感受性というものですが、感受性は測りようがない。クオリアの領域に入ってしまいますから。測りようがない、比べようがない、だからそういうものには目を向けない。ないことにする方が楽だという傾向にどんどんなっている。
音楽がきちんと言葉で説明できるなら、音楽は要らないんです。言葉で表現できないものを表現するために、芸術というものがある。
久石:そうですね。養老さんにそう言われると非常に説得力があります(笑)。
養老:感覚自体が落ちてきているんですよ。単純な形で測れないものの重要性が見落とされている。それは、音楽の世界なんかに非常に響いてきているでしょうね。
耳はものを聴く以前に、運動器官である
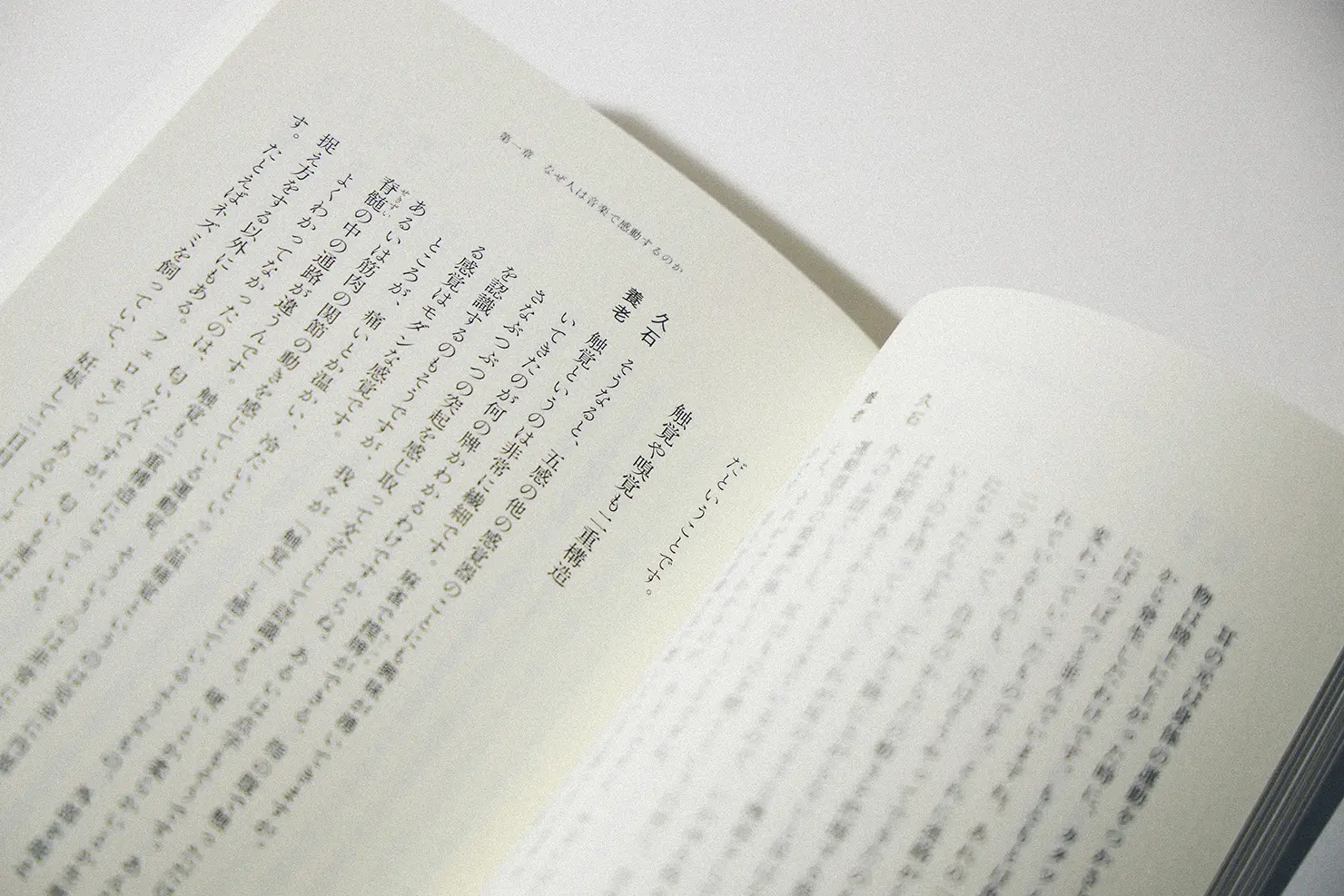
養老:考えてみると、感覚器というのは必ず二つ存在しているんです。こういうこと言うのは僕だけなんだけど。
久石:ん? ということは、目が二つ、耳も二つ、鼻の穴も二つということではなさそうですね。
養老:うん。どういう意味かというと、目という器官があって網膜にものが映し出されていろいろなものが見えているわけですが、そういった外の世界を捉えているのとは別に、自分のからだにとって必要な目があるんです。それが第二の目です。
たとえば「日周活動」。朝になると、明るくなって目が覚めて、夜になると眠くなる。これをコントロールしている目がある。それを「松果体」というんですが、松ぼっくりみたいな形をしていて、脳のど真ん中にある。これが、実は体内の「目」の働きをしている。松果体が光を採ってないのは、哺乳類だけです。
鳥でもちゃんと松果体は目として機能しています。上に骨があって皮膚があり、羽が生えていますけど、そこを通り過ぎてくる光をちゃんと感じているんですね。朝と晩の違いがわからなかったら、活動に影響するでしょう? つまり、「自分のからだに関する目」は別にあるんです。
人間も、光を取り込んではいませんが、松果体の中に光を感じる細胞が今でもちゃんと残っているんです。どうしてそれが光を感じるかがわかるかというと、松果体の細胞は、網膜にある細胞と同じように光をトラップする特殊な構造を持っていましてね、それでわかる。
では耳はどうか。耳にはちょっと特別なところがある。耳の元は身体の運動をつかさどる平衡器官。いわゆる三半規管がそれですね。動物は陸上に上がった時に発生したわけです。もともとは魚の頭のところにあったものが、特殊に変わっていったものです。
自分のからだの動きを把握する「前庭器官」(編集部注・三半規管)に、音を聴くものがついて耳になったんです。
久石:今のお話でいうと、耳はものを聴くという以前に、自分のからだの動きを把握する運動器官の要素が強いということですね。
養老:ええ、それがよくわかるのが、めまいですよ。めまいは三半規管の働きで起きるものです。音とか音楽を耳で聴いていると思っていますが、振動をからだのいろいろなところで聴いているので、必ずしも耳だけで聴いているわけではありません。
耳は外の世界を捉えるばかりではなくて、からだの内側にも深くかかわっている器官だということです。
久石:そうなると、五感の他の感覚器のことにも興味が湧いてきますが。
養老:嗅覚器を調べてみると、実は「ヤコプソンの器官」といって、古くからの器官なんですが、この器官で哺乳類は間違いなくフェロモンを感じている。人間では胎児の段階ではあるんですが、大人になると退化するともいいます。
音楽で人が感動しやすいわけ

養老:ここまで話せばピンと来ると思いますが、すべて、感覚器は二重構造になっているわけです。松果体もヤコプソンの器官も、退化傾向にある。だけど、耳だけは、三半規管は退化できません。いわば古い感覚器が耳だけは非常に強く残っているんですよ。身体の運動に直接つながっていますから。
脳の中では当然、近い関係にある。つまり脳からいうと、聴覚は古いところに直接届いている。それがいわゆる情動に強く影響するということなんです。
久石:ほおおお、面白いなあ。
養老:情動というのは、実は脳でいうと古い部分といわれている「大脳辺縁系」にかなり大きな影響を与える。実は、それが一番遠いのは目なんですよ。目は非常に客観的。だから、見て感動するより、聴いて感動する方がよっぽど多いんです。
久石:長年の疑問が解けました。う~ん、そういうことだったんですね。
養老:それをドイツ人は経験から知っていたんだと思います。ニーチェは、最初に書いた『悲劇の誕生』という本で、ギリシャ悲劇というのは、目で見る舞台と耳で聴くコーラスと両方からできているという二重性を説明しています。
視覚から入ってくる方は、明晰な美しさを持ち、均整といったものを中心にしている、それに対して音楽は強くて暗くて、強く人を動かす。それを彼は「アポロン的」と「ディオニュソス的」というふうに分けた。その二つの組み合わせによってギリシャ悲劇はできているのだといったことを二十代の若さで書いている。
久石:そうですね。伺っているうちに、これまで僕が頭の中で断片的に考えていたことが綺麗につながった気がします。ニーチェは自分でピアノも弾いていたし、作曲もしていました。
ですから、僕はニーチェの文章を読んでいてちょっと理解できないなと思う時、音楽を想定して考えるんです。そうすると「ああ、これはひょっとしたらこういうことかなあ?」となんとなくわかってくるようなことがありますね。
生きていく時に基本になるのは目よりもむしろ耳
久石:今の時代、視覚偏重とまでは言いませんが、目から入ってくる情報にものすごく依存度が高くなっている気がしていたんですが、こうしていろいろ伺って、聴覚の力、耳の果たす役割をあらためて見直すことになりました。
養老:ちょっと乱暴な言い方だけど、おそらく根本的なところで、生きていく時に基本になるのは目よりもむしろ耳の方でしょうね。意識を失った人が意識を取り戻す時も、最初に耳が回復する。声が聴こえてきて、次に目が開くんです。死ぬ時もたぶんそうです。
久石:ああ、『チベット死者の書』なんかもまさにそうですね。死んでいく人の耳元でずっと語りつづけられる。死後四十九日間にわたって経典が読まれ、それが死へのプロセスになっているという。意識が遠のいていく時に、最期まで耳は聴こえているんですかね?
養老:死んでみたことがないからわからないけどね。「ご臨終です」という声なんかが聴こえていて、「あれ? 俺、ご臨終なのかぁ……」と感じるのかもしれませんよ(笑)。
『脳は耳で感動する』

著者:養老孟司、久石譲
価格:1,760円(税込)
四六判 248ページ
ISBN 978-4-408-65131-6
養老孟司
1937年鎌倉市生まれ。解剖学者。東京大学医学部卒業後、同大学院博士課程修了。東京大学医学部教授を経て、1996年から2003年まで北里大学教授を務める。東京大学名誉教授。1989年『からだの見方』でサントリー学芸賞、2003年『バカの壁』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。『唯脳論』『養老先生、病院へ行く』『ものがわかるということ』など著書多数。
久石譲
現代音楽の作曲家として活動を開始し、音楽大学卒業後ミニマル・ミュージックに興味を持つ。近年はクラシック音楽の指揮者として国内外のオーケストラと共演。ドイツ・グラモフォンからリリースした「A Symphonic Celebration」は米国ビルボード2部門で1位を獲得した。2024年4月、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団Composer-in-Association就任。25年4月、日本センチュリー交響楽団音楽監督に就任。
Photos:Soichi Ishida
Edit:Kozue Matsuyama


