柴田碧と西山真登により2015年に結成されたDTMユニット、パソコン音楽クラブ。 往年のハードシンセや音源モジュールを駆使しながらクラブミュージックとポップスが交錯する音世界を紡ぐ2人は、昨年にはフジロックフェスティバルへの出演も果たし、今年5月にはchelmicoや髙橋芽以(LAUSBUB)らをフィーチャーした4thアルバム『FINE LINE』をリリースするなど、着実にキャリアを積み重ねている。 そんな彼らに、ハード機材との出合いや制作環境の変遷、折衷的な音楽性を育んだ地元大阪のシーンなどについて、柴田のプライベートスタジオで話を聞いた。
ハード機材を使用するようになったきっかけとデジタルシンセの魅力
Roland SCシリーズやYAMAHA MUシリーズなど1990年代の音源モジュールやデジタルシンセサイザーといったハード機材を用いて音楽制作を行なっていることを公言されていますが、どういったきっかけでハード機材を使用するようになったのでしょうか?
柴田:パソコン音楽クラブを始めたのは、お互いが大学三、四年生の頃ですね。 元々一緒にバンドをやっていたんですけど、卒業間際くらいの時期になるとふたりとも時間を持て余していたこともあって、よく一緒に楽器屋さんに行っていました。
あと当時の大阪のソフマップには中古の音源モジュールやMIDI機器を取り扱っているコーナーがあり、そういった機材が3,000円〜4,000円くらいで叩き売られてました。 また、ハードオフでも同じような機材が安く販売されていたので、そういった機材を購入して作った曲をSoundCloudにアップしてお互い聴き合うようなことをしていたのですが、その時にアカウント名を “パソコン音楽クラブ” と名付けたことが活動を始めるきっかけになりましたね。
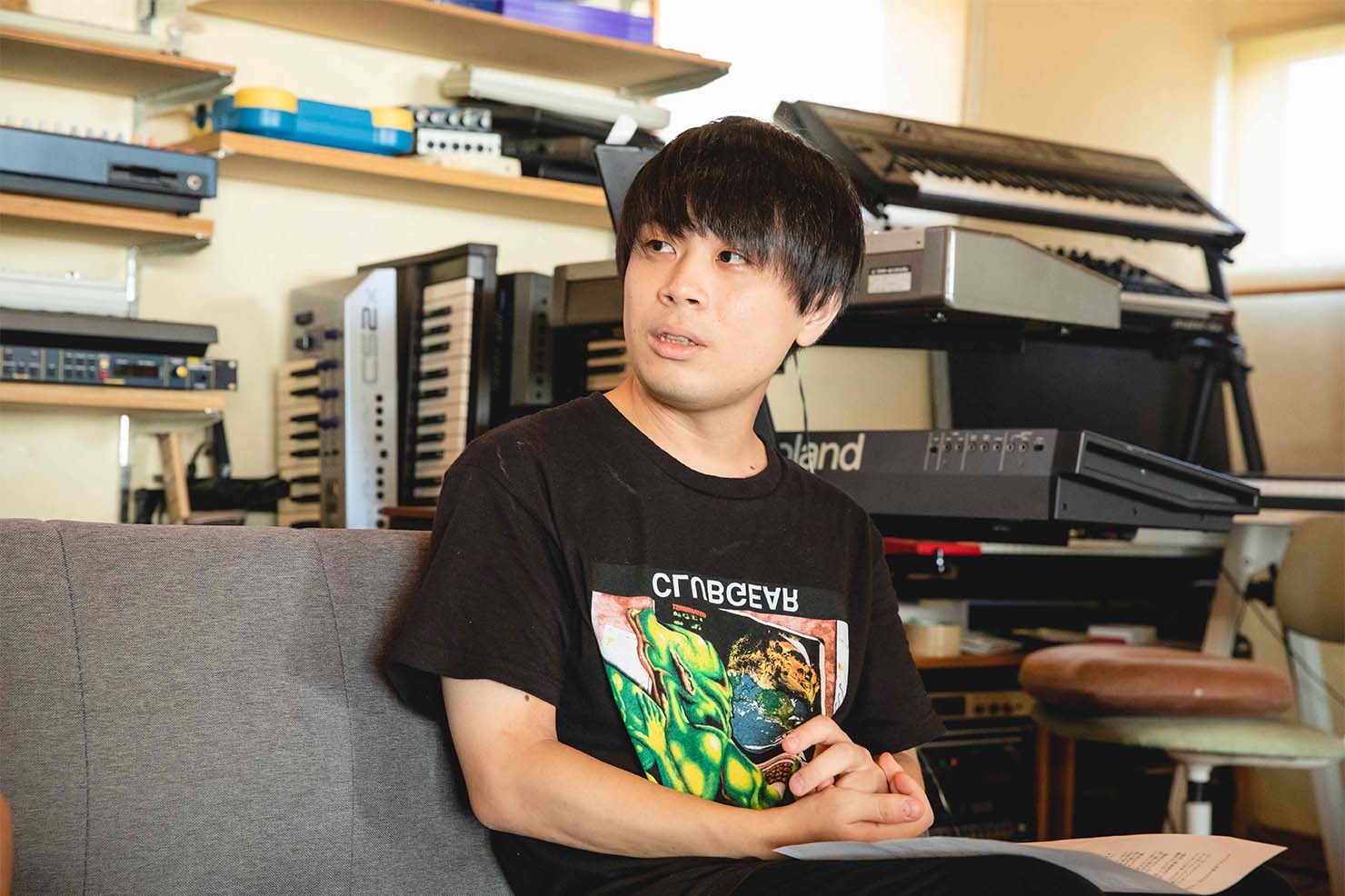
西山:当時は今ほどそういった音源モジュールにスポットライトが当たっていなかったこともあって、中古機材の価格もそれほど高くはなくて。 例えば、中古の「Roland JV-880」だと5,000円くらいでしたし、「Roland SC-88Pro」でも1万円くらいで購入できました。 そういう意味では、中古ハード機材が手に入りやすい時期だったと思います。

柴田:今思うと学生がハードオフで何か面白い音楽を求めて、100円CDを買う感覚に近かったと思いますね。


西山:それとデジタルシンセ自体に最初にハマった理由は、単純にアナログシンセよりもデジタルシンセの方が安く購入できたからです。 1万円あれば、ふたつ購入できる中古のデジタルシンセはお金のない大学生だった僕らにはすごく魅力的でしたね。
現在はAbleton Liveも使用されているとお聞きしましたが、その頃は音楽制作にDAWは使っていなかったのでしょうか?
西山:作曲目的というよりは、録音するためにMTR感覚でDAWを使っていました。
柴田:その頃はNative Instrumentsのソフトシンセ「Massive」を使って、遊びでDTMをやることもありました。 ただ、そういったものよりももう少しチープな音で曲を作りたいと思ったこともあって、中古のデジタルシンセを購入することにしました。
西山:デジタルシンセの豊富なプリセットは、当時の僕らからするとすごく魅力的でしたし、プリセットを切り替えて新しい音が出てくるあの感じは、知らないアーティストのCDを買って曲を1曲ずつ探すときに似たときめきがありましたね。 それが宝探しをしているかのようですごく楽しかったことを覚えています。
なるほど。 その体験があったからこそおふたりがデジタルシンセに傾倒していくことになったのですね。
柴田:僕らがデジタルシンセを使い始めた理由としてはそれがすごく大きいです。
西山:例えば、当時のPCM音源のデジタルシンセに入っているプリセット音源をDAWに取り込んでフィルターをかけていじるだけでもすごく面白い音になるんですよ。 だから、当時はレコードの音をサンプリングする感覚でプリセット音源を録音したあとにそれを切り刻んだりして、フィルターハウス的な曲を作っていましたね。
「ここ数年はアナログシンセの活躍の場が増えている」

現在、音楽制作において欠かせない重要な機材や特にお気に入りの機材はありますか?
西山:ここまでデジタルシンセの話をしていたから、これはちょっと裏切りかもしれませんが、実はここ数年はアナログシンセをよく使うようになりました(笑)。 もちろんデジタルシンセも好きだからたまに使うんですけど、デジタルシンセの場合は、最近のRoland Cloudのようなモデリング音源のソフトシンセでもそこまで音色としては変わらないので、そっちを使うことも多くなりましたね。 ただ、アナログシンセの場合は個体差やCVで走らせたときの音の変化にも違いがあったり、実機じゃないと出ない音がやっぱりあるんですよ。
柴田:今使っている「Roland Juno-106」や「Sequential Circuits Prophet-600」、「KORG MS-20 mini」のようなアナグロシンセは、インタフェースが楽器だから自分の操作を直感的に音に反映できるというか。 特にDAWのマウス操作では作るのが難しいSE音のような音を作る時は本当に重宝しています。 そういう音を作る場合、ソフトシンセだと意外と頭の中で色々ルーティングしないと作れないんです。 でも、アナログシンセだとツマミをちょっと捻るだけですぐにそういう音が鳴るので、自分がやりたいことを反映しやすい部分はありますね。
西山:ただ、実際には実機のアナログシンセとソフトシンセをケース・バイ・ケースで使い分けています。 一時期は全部実機でやっていましたが、単純に作業時間の面で妥協してソフトシンセを使うこともあります。
あと重要なシンセということであれば、やっぱり「Roland TB-303」は外せない機材です。 シーケンサーが独特というか、すごく意地悪なんですけど、そこがこの機材が絶対に実機じゃないといけない理由です(笑)。

柴田:TB-303の実機にはディスプレイもないし、正直この中で何が起こっているかわかりにくいのですが、それがソフトシンセになると明確に打ち込めてしまうんです。 だだ、そうなると実機ならではの入力方法から生まれる固有の粘りというか、グルーヴが損なわれてしまう気がして。 だから、使うとなれば、ツマミを捻るなどフィジカルに操作しながら感覚的に音楽が作れる実機を選びます。
そういったこだわりがあるTB-303ですが、音楽活動を始めた当初から実機を使用されていたのでしょうか?
西山:いえ、最初はSC-88Proでわざわざ再現していました。 でも、そういった90年代の機材に入っている “303 Bass” のようなプリセットのTB-303系の音って、すごくペラペラでビヨビヨしていたり、全く本物に似ていなくて音的にはすごく酷いんですよ(笑)。 でも、全くの別物だからこそ、当時は逆にそれを面白がって使っていましたね。
柴田:元々僕らはデジタルシンセから曲作りを始めたこともあって、昔のフュージョンやシティポップで使われていた「YAMAHA DX-7」のようなFM音源の音をかっこいいと思っていました。 それと当時でもTB-303の実機は手が出せないくらい高価でしたし、バンドの延長で音楽をやっていたので、TB-303を使ってアシッドハウスをやるという考えはありませんでした。
では、実際にTB-303を手に入れたのはいつ頃でしょうか?
柴田:興味を持ち出したのは、ハウスやテクノをやっている周りの人の影響があってのことですが、実際に手に入れたのは2ndアルバム『Night Flow』をリリースしたその後くらいかな? はっきりとは覚えていないんですけど、おそらく2020年か2021年には手元にあったと思います。
西山:TB-303の実機自体は、元々中古市場でも高値で取引されていましたが、その頃になると値段もかなり高騰していましたね。 多分20万円くらいだったと思いますが、それでも今よりは全然安かったと思います。
Juno-106を使用されているとのことでしたが、こちらも同じ頃くらいから使用されているのでしょうか?
柴田:手に入れたのはパソコン音楽クラブを始める前ですね。 調子が悪いからもう使わないということで地元の友達のおばあちゃんの家にあったものを譲ってもらいました。 そこから一度も修理に出していませんが、今でも全然使える状態です。
西山:その頃はさっきも言ったようにデジタルシンセに興味があったのであまり曲作りには使っていませんでした。 実際に僕らがアナログシンセの良さを再発見したのは『Night Flow』以降です。
ハード機材ならではの魅力はどこに宿るのか

ソフトシンセで音楽を作るのとアナログシンセなどハード機材で音楽を作ることの違いはどういったところにあるのでしょうか?
柴田:やっぱりマシンありきというか、ソフトシンセを使う場合でも実機が一瞬、頭の中に浮かぶんです。 僕らにとっては、実機から音が発せられていることが重要で、そうあることで自分の中で音色のイメージやそれに付随するものが変わってくるというか。 シナプスの回路が全然違うものになっていく感覚があって。 だから、同じ音が出たとしても、ソフトシンセと実機では最終的にアウトプットされる音が変わってくるんです。
なるほど。 では、具体的にどのようなところにハード機材の魅力を感じますか?
柴田:筐体自体の見た目のマシン感にかわいさを感じられる点ですね。 音だけでなく見た目も含めてテンションが上がるというか、音色ひとつひとつに愛着が湧いてきます。
現在はモジュラーシンセやハード機材を制作やライブで使用するアーティストも増えてきましたが、若い世代のアーティストはPCだけで完結させてしまう人も少なくありません。 おふたりはPCとハード機材を併用しながら音楽を作っているとのことでしたが、その制作スタイルのメリットを教えてもらえますか?
柴田:自分の中でDAWはシーケンスを組み立てる作業にすごく向いているんですけど、例えば、ドラムマシンを鳴らしてツマミを捻ったりしながら、遊び感覚で曲を作りたいときはハード機材を使うケースが多いですね。
一方でクライアントワークなどちゃんとした音楽を作らなければいけないときはソフトシンセを使っています。 そういう意味では自分たちの個性を出したい場合はハード機材、ちゃんとした音楽を作るときはソフトシンセという感じでツールを使い分けています。 あとさっきも言ったように筐体がかわいいとか、見た目重視でハード機材を使っている部分はありますが、実際にハード機材を使うことでイメージが膨らむこともあります。 一方、ソフトシンセから作る方が面白い場合ももちろんあります。 そこは場合によって違うので、選択肢としてこのふたつを使いわけています。
西山:僕の場合は、正直どっちでもいけます。 ただ、ハード機材とソフトシンセでは鳴る音自体は絶対に違うため、ハード機材でないと替えが効かないものに関してはそちらを使うようにしています。 もちろん、昔はハード機材をひとつずつ鳴らしていき、ときめきを感じた音色を使っていたので、今でもそういうやり方は続けていきたいという想いはありますよ。 でも、今はもっとドライに判断しているというか、鳴らしたい音ありきでそのための機材をハード、ソフト問わず選んで使っていますね。
“ソフト音源化されていない音”=家庭用キーボードの魅力とは

柴田:今はいろいろなメーカーが昔のハード機材の音をソフト化していますが、その中でもスポットライトが当たっていない機材は当然あります。 そのひとつが家庭用キーボードで、例えば、CASIOのものだと「スレンテン」で使われたもの以外はあまりスポットライトが当たっていないんですよね。
西山:ちなみに家庭用キーボードで一番有名なのは多分「CASIO SK-1」だと思いますが、僕らは同じメーカーの「SK-8」も所有しています。 あと「YAMAHA PortaSound」も割と面白い音が入っているのですが、この辺りの機材はどこもソフトシンセ化や音源化していません。 こういう機材を見つけるとすごく嬉しい気持ちになります。
柴田:家庭用キーボードに関しては、まだハードオフで安く販売されていますが、SK-1は以前と比べるとかなり高くなった印象があります。
西山:家庭用キーボードの音は、ビットレートが低いのか、ザラっとした質感のものが多い。 だから、それをサンプリングして、Spliceの解像度が高いドラム音源と混ぜて使うことで音に癖を出していくのも楽しかったりもします。
制作時におけるDAWの役割

先ほどDAWをシーケンサーやレコーダーとして使っているという話もありましたが、それ以外に何か特徴的な使い方をしていますか?
西山:僕らは普段、デジタル、アナログ関係なくハードシンセの音をDAWに取り込んだ後にめちゃくちゃ加工することもあって、直感的にオーディオを扱えるAbleton Liveだと作業がすごくやりやすいんです。 そういう意味ではAbleton Liveをエフェクターとして使っている部分はありますね。
柴田:あと制作時だけでなく、ライブセットを作る時もAbleton Liveを使っています。
普段、どのような形で制作作業を分担されているのでしょうか?
柴田:基本的にはどちらかが最初にデモを作って、何度かやりとりをした後に構成を組んだり、曲自体をブラッシュアップしていくやり方です。
西山:柴田君のスタジオにはいろいろなシンセがあるので合宿みたいに集まって作業することには向いています。 だから、ここである程度曲を作ってから、ミックス作業とそのチェックを僕のスタジオでやるようにしてます。
僕のスタジオはかなり吸音材を使っているので、ドライで聴ける環境になっていますが、そういう音はミックス作業には向いていても無味乾燥な音なので、楽しみながら作業するのにはあまり向いていないんです。 だから、柴田君のスタジオはふたりでラウドな音を聴き、気分をアゲながら制作する場というか、それぞれのスタジオをそういう形で使い分けています。
あと作業内容的には柴田君の方が編曲的なアプローチが上手なので、彼になんとなくこっちで作ったものを投げて、丁寧にブラッシュアップしてもらうこともあります。 逆に僕はミックス作業などサウンドデザインの方が得意なのでそっちの作業を担当することが多いですね。
最新作『FINE LINE』で新たに導入された機材

2023年5月に最新アルバム『FINE LINE』をリリースしていますが、同作の制作のために新たに導入した機材はありますか?
柴田:『FINE LINE』制作時は、新たにミシンやプリンターで有名なbrotherの電子オルガンを導入しました。
西山:そのサンプリングした音をAbleton Liveのサンプラープラグインの「Simpler」に入れて、「Day After Day feat. Mei Takahashi」の印象的なフレーズを作りました。 それと「It’s(Not)Ordinary feat.MICO」では、曲全編に渡ってこれに入っているプリセットの音を使っています。

柴田:ただ、この機材を導入することになったのも、たまたまハードオフですごく安く販売されていたのを発見したからです。 それで購入して実際に音を鳴らしてみたところ、相性が良かったというか。 『FINE LINE』からどことなく漂うレトロ感のある音の多くはこの機材のものなので、そういう意味ではアルバムを象徴する音になったと思っています。
アルバムを象徴する音ということであれば、これまでのパソコン音楽クラブのアルバムには一枚ごとにそういった音があるように思います。
柴田:そうですね。 『DREAM WALK』だとSC-88Proですね。
西山:僕はそのときは鍵盤付きのSK-88Proを使っていましたが、DAWのマスターキーボードもそれを使っていましたね。 今は使う機会が減りましたが、その頃はめっちゃ使っていました。 あとJV-1080もよく使っていました。
柴田:『Night Flow』では「KORG 03R/W」をよく使いましたが、これは吉祥寺のハードオフで当時4,000円くらいで販売されていたものだと思います。 音がすごく良かったので、これを使えばアルバムのカラーになると思いましたね。 あと『See-Voice』だとProphet-600かな。 ポリフォニックのアナログシンセですが、デジタルシンセだけでなく、アナログシンセも使ってみようということで導入したものです。
西山:それと「KORG M3R」ですね。 その中にマルチで鳴っているラックの音があるんですけど、パッドの音とシャカシャカみたいな音とか、泡や水のように感じる音が混ざったような音を使いました。 あとこのアルバムでは、夜の帰り道や夜中の街のテイストを出したかったので空気の音を入れたいと思っていました。 そのためにM3Rや03R/Wに入っているパッドとノイズのシューみたいな音が混ざった音を多用したのを覚えています。 それがこのアルバムの象徴的な音になりましたね。
あと、『See-Voice』では88Proも使いましたが、以前とは違う使い方をしています。 例えば、『DREAM WALK』だと何でも88Proという感じで使っていましたが、そのヘロヘロな音が当時流行っていたヴェイパーウェイヴ的に捉えられたおかげで僕らの音楽が評価された部分はあると思います。 でも、『See-Voice』の「潜水」という曲では、88Proのエレピの音にピンポンディレイをかけるという、レイ・ハラカミさんオマージュ的な使い方もしましたね。
2人の折衷的な音楽性を育んだ関西のボーダーレスな音楽シーン

クラブミュージックの文脈を踏まえながらもポップスとして成立する音楽性を確立されていますが、その音楽性に至った経緯を教えてもらえますか?
柴田:僕らが大学生の頃はインディーロックがすごく流行っていて、それとシューゲイザーが結びついたり、チルウェイブやMaltine Recordsのようなネット音楽もすごく人気でした。 また、その頃拠点としていた関西では、そういった音楽がボーダーレスに絡み合うイベントもあって、とにかくすごく盛り上がっていたんですよ。
西山:だから、そういうテクノではなく、もう少しインディーロックっぽい文脈でシンセを使う人たちのコミュニティーの中に僕らはいたので、ダンスミュージックっぽい身体性を追求したものよりも、もう少しシューゲイザー的にガッと没入できる音楽の中で育った感じの方が強いんです。 そのこともあって歌モノとかポップな感じは、割と活動初期から自然と受け入れてきましたね。
柴田:そういう意味では僕らの中ではクラブと宅録が渾然一体となっていたと思います。 だから、当時はDâm-Funk(デイム・ファンク)やOmar-S(オマー・S)のような ”DJツールとしてはローファイすぎるけど、リスニングとしては素晴らしい” みたいな音楽を面白がってよく聴いていましたし、自分たちの周りで流行っていたこともあって、それが当たり前だと思っていました。
西山:でも、今はクラブにもよく行くようになったことで、当時は理解していなかったツールミュージックとしてのダンスミュージックの良さも理解できるようになりましたし、クラブでかけるための音質も意識するようになりました。
当時の関西におけるボーダーレスなシーンの存在は、おふたりのキャリアにおいても大きな影響を与えているんですね。
西山:そうですね。 そういった “クラブ鳴り” を意識していない、ヘロヘロな質感の音楽でも許容してくれるシーンがあったからこそ、バンド感覚で歌モノ入りの1stアルバムを作ることができたと思っています。
柴田:あとその当時の東京にも、Maltine Recordsや秋葉原MOGURA周辺には近いシーンがありましたね。 2017年頃に初めて秋葉原MOGURAでライブをしたのですが、その時にそこにおられたtofubeatsさんと知り合いになりました。
西山:それ以来、tofubeatsさんには後輩として可愛がってもらっていますが、僕らとしてもライブのスタイルだったり、ダンスミュージックの上でポップス的な音楽をやるというバランス感覚だったり、tofubeatsさんはから多大な影響を受けました。 本当に当時の僕らにとってtofubeatsさんはロールモデルでしたね。
これからハード機材を使ってみたい人に向けて、何か機材を選定する上でのアドバイスをいただけますか?
柴田:見た目で使ってみたいと思える機材の方がより深くのめり込めると思うので、まずは自分のテンションがアガる見た目のものを選んでほしいですね。
西山:そもそもDAWがあれば、内蔵音源だけでも曲作りができてしまう今の時代において、わざわざハード機材を使ってみたい人というのは、一念発起してやってみたい人か、もしくは趣味で使ってみたい人だと思います。 だから、そういう目的があるのであれば、音よりも見た目重視で好きな機材を選んでみるのも楽しいと思います。
柴田:あと趣味であれ本業であれ、ギター少年が自分の憧れのギタリストが使っているギターを使うように、自分が好きなアーティストが使っているハードシンセを使うことがあってもいいと思いますね。
以前からオーディオテクニカのヘッドホンを使用されているとお聞きしていますが、現在はどのモデルを使用されているのでしょうか?
柴田:今はオープン型のATH-R70xをメインで使っていますが、少し前まではATH-M50xも使っていました。 そちらはスタジオでのモニタリング用だけでなく、他の用途でも結構使っていましたね。

西山:僕も以前はATH-M50xを使っていましたが、使い始めたのは『Night Flow』をマスタリングしてもらったエンジニアの得能直也さんから「コスパが良くていい感じのヘッドホンがあるよ」と教えていただいたのがきっかけです。
でも、今はもう少しスピーカーライクな低音が聴こえるものがほしかったこともあって、ATH-R70xを使っていますが、軽くてつけ心地がすごく良いところも気に入っています。 特に僕の場合は普段から眼鏡をかけているので、しっかり耳に密着するタイプのヘッドホンだと長時間つけているとだんだん痛くなってくるんですよ。 でも、ATH-R70xだとそうならないのでありがたいですね。
パソコン音楽クラブ
2015年結成のDTMユニット。 メンバーは⼤阪出⾝の柴⽥碧と⻄⼭真登。 往年のハードウェアシンセサイザー・⾳源モジュールを⽤いて⾳楽を制作している。 他アーティスト作品への参加やリミックス制作も多数⼿がけており、ラフォーレ原宿グランバザールのTV-CMソング、TVドラマ「電影少⼥- VIDEOGIRL AI 2018 -」の劇伴制作、アニメ「ポケットモンスター」のEDテーマ制作など数多くの作品も担当している。 演奏会も精⼒的に⾏っており、FUJIROCK2022へも出演し話題になる。 2018年に初の全国流通盤となる1stアルバム『DREAM WALK』をリリース。 2019年、2ndアルバム『Night Flow』は第12回CDショップ⼤賞2020に⼊賞し注⽬を集める。 2021年10⽉には3rdアルバム『See-Voice』をリリース。 2023年5月10日に4thアルバム『FINE LINE』をリリース。 11月22日には彼らと親交のあるアーティスト達が『FINE LINE』を再構築したREMIXアルバム『FINE LINE Remixes』をリリースする。
Words:Jun Fukunaga
Photos:Kentaro Oshio
Edit:Takahiro Fujikawa


