インドには3年おきに開催される、ガンジス川などの聖なる川が流れる4つの都市を巡回し、沐浴を行う「クンブ・メーラ」というヒンドゥー教徒の平和の祭典がある。
2025年はシヴァ神を祭る催し「シヴァラートリー」とも重なることから、実に144年に一度の大祭典となり、合流地点であるプラヤーグラージに世界中のヒンドゥー教徒が集結した。そんな機会を逃すまいとインドへと足を運んだのは、東京・学芸大学でインド・ゴア地方の料理を提供する「表面張力」の店主、加藤伊織さん。興奮冷めやらぬうちに、かねてより彼と交流があるWATARIGARASUの倉本潤が北のデリー、東のバラナシ、南のゴアと各地を巡った加藤さんの魂を揺さぶるインド旅「インド放浪記」の全貌を訊いた。
後編では、前編のバラナシから移動した旅の最終目的地、ゴアの様子を紹介する。
独自の進化を遂げる町、ゴア。



加藤さんの今回の旅の目的は、インドの「食」を体験することでもありましたよね。
インドという巨大な国を動かしているとも言える「食」の存在には、常にアンテナを張りながら旅をしてきましたね。インドは地方によって料理のスタイルが多様に変化するんですが、今回はヒンドゥー教の食べ物を中心に見てきました。まず北インドは、ほとんどの料理にオイルと塩が多用されているのが特徴で、「オイルと塩が人々を動かしている」と言っていいほどなんです。
では逆にゴアまで南下すると、どのように変化するのでしょう?
南下すると、小麦よりも米が主食になってきて、加えて発酵食品も頻繁に使われるようになります。ゴアはインドの西海岸で、アラビア海に面した州なので、シーフードが有名なんですけど、ポルトガル領だった歴史もあり、西洋文化も入り混じった独特の文化が形成されているんです。「ポークビンダルー」という酸味を効かせたカレーは日本でも有名ですが、発祥の店はゴアにあったりします。
ただ今回は、「インディアンチャイニーズ」という、インド中華料理を掘りに行くことが旅のひとつの目的でした。インドには中国人の移民が約3万人いて、その人たちが持ち込んだ中華料理が伝播して、焼く、蒸す、揚げるなどの中華の技法に、インドのスパイス文化が加わり、独自の進化を遂げているんです。野菜や鶏肉を団子状にして濃厚なソースで炒める満州仕込みの「マンチュリアン」、四川の辛味を効かせた「シェズワン」、ほかにも香港風、シンガポール風と大体この4つに分かれるみたいなんですけど、特にゴアは、お酒を飲む文化が強くて、カシューナッツの蒸溜所やジン、クラフトビールなんかもたくさんつくられているので、その二次的に生産される発酵調味料による味つけの炒め物も多かったです。ポークビンダルーの豚肉を煮込むワインビネガーもそのひとつですね。

一昨年、ゴアで出会ったシェフの友人が家に招いてくれて、そこで「ゴアンタリー」という、インドの魚定食のようなワンプレート料理を教わり、地元の飲み屋にも連れて行ってもらったんですが、お酒と一緒にインディアンチャイニーズが食べられるレストランも結構ありました。


インドと言えば、豊富なスパイスを連想してしまうのですが、何か目を惹くスパイスには出会えましたか?
フルーティな香りと鮮やかな色味を出してくれる、ゴア料理には欠かせないカシミールチリをたくさん買ってきましたね。日本だとかなり高値で取引されているんですけど、やっぱり現地は安かったです。その一方でレシピも売っていたりするんですけど、それは10万円ぐらいしていましたね。スパイスの種類も豊富でしたが、その組み合わせは地方によってもさまざま。

それと同じように、インドの公用語にはヒンディー語と英語があるものの、州ごとに運用されている主要言語は22言語にも及び、2001年時点で、メジャー言語は122語、マイナー言語に至っては1500語以上存在していて、文字は一緒でも、場所によって全然読めなかったり、意思疎通がとれないことがあるらしいんです。それがいい意味で独自の文化を守り、発展させているんだと思いますが、州を跨ぐと別の国に来たような感覚があって、食文化も多種多様。言語が画一化されれば、失われてしまう文化もあるのかもしれないですよね。
そういう意味では、徐々に方言がなくなりつつある日本の状況が何だか寂しくもありますね。
食以外では、ゴアの町をどのように楽しんできましたか?


ゴアの町はところどころでさまざまな人が集まっていて、ある場所では金曜日だけ開催しているヒッピーマーケットで賑わっていました。三軒茶屋の三角地帯で若者が飲んでいるような雰囲気の場所があったかと思えば、その裏に往年のヒッピーたちがいたり、はたまた中目黒を彷彿させるエリアまであって、レコードバーやデザイナーの女の子がやっている焼き物屋、スペシャルティコーヒーを出している店と、結構自分と感覚が合うような人たちもいたんです。ただ、そこで安心してしまっては何も得られないので、なるべく迷子になる努力をしていましたね。
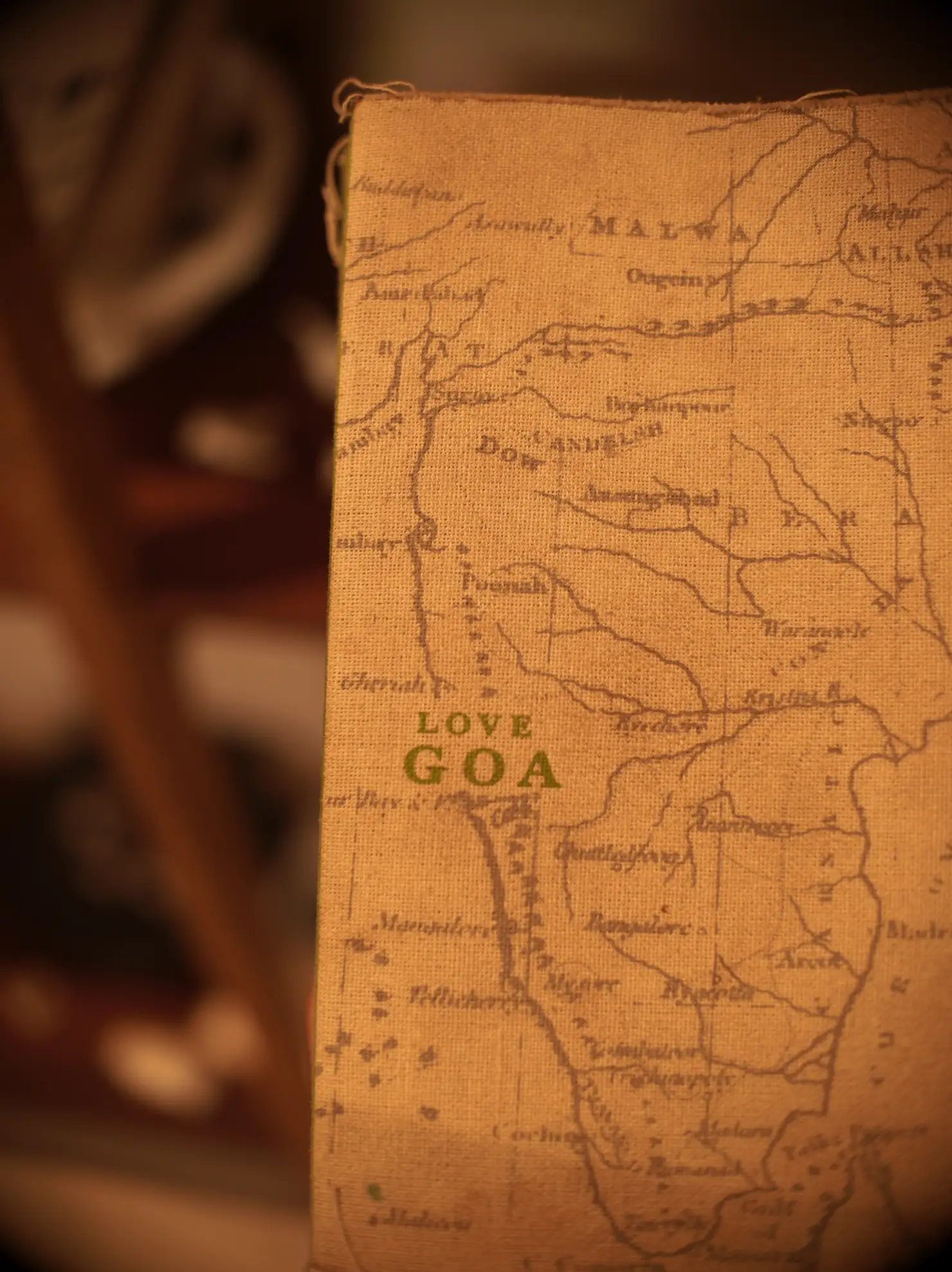
あとは何と言ってもビーチパーティーですよね。ゴアはやっぱりパーティー文化が盛んな場所なので、ビーチによって特性の異なるパーティー文化が根ざしているんです。縦に延びた海岸線の一番北には、ヒッピーカルチャーが色濃いドレッドヘアの人たちがジャンベを叩いたりするアランボルビーチ、その下には、パーティーシーンど真ん中といった感じのアンジュナビーチ、ビーチだけでもたくさんあるので、「Party Hunt」というゴアのパーティー情報が集まるアプリを見ながら、みんな行きたいパーティーの情報を取得していて。ライブを観たり、DJの音楽を夜通し聴いたり、ゴアでは自分の好きな遊び方を探しながら楽しむのが肝ですね。


「食」という、アナログ文化。
話をパーティーに戻しますが、ゴアと言えばヒッピーの聖地でもあり、ゴアトランスというトランスのいちジャンルを生んだ場所でもありますよね。
そうですね。今回は、もともと渋谷でアパレルの仕事をしていた日本人女性にゴアをアテンドしてもらったんですけど、彼女はトランスが好きでゴアに来たらしいんです。ゴアトランスというジャンルが確立されたのは90年代ですけど、70年代からヒッピー文化の聖地だったゴアにすっかり魅了されたみたいで、現地でイスラエル人の旦那さんと結婚して、かれこれもう20年以上ゴアに住んでいるんです。
面白いエピソードがあって、それは彼女が “パーティーシューズ” を売って暮らしていたこと。以前、それがパーティーシーンで一世を風靡したんですが、そのパーティーシューズというのが、岡山から仕入れた足袋だっていう(笑)。いまは下火にはなったみたいなんですけどね。それで、今度は “食こそ一番のアナログ文化だから” と飲食店をはじめたみたいなんです。
今度は飲食ですか(笑)。何でも仕事にする気概が逞しいですね。
ゴアに限らない、インドのいいところは、ビジネスをはじめるルールに余白が多く、それゆえ自由度が高いところなんですよ。日本だとまず保健所のルールに従った事務作業があって、店を開けるまでに多くのステップをクリアする必要があるし、店をはじめるまでは人が来てくれるかわからないから、出店までのハードルって結構高いじゃないですか。でも、ゴアはとりあえず足袋を仕入れて布を敷いて広げれば、そのまま売り始めてしまえるような空気がある。それがダメならほかのモノを仕入れて売ればいいし、日本と比べると商売のハードルはかなり低い。当然、自己責任ではありますけど、それで成り立つんです。もちろん、状況は見続ける必要はあるけど、退屈な時間なんてどこにもなくて、予測不能な毎日を生きることに必死になるわけで。彼女はいつも「インドでは常に考え続けないと生きていけない」と言っていたんですが、そんな能動的な姿勢がインドの良さなのかもしれないですよね。

予定調和ではなく、予測不可能な状況が常にあるのがインドなのかもしれません。
彼女はゴアの管理され過ぎていない状況が好きで暮らしているんだと思うんです。でも、何よりも大きいのは人口ですよね。人口が多く、購買意欲も盛んだから、とりあえずで商売したとしても成り立つ環境がある。なかには道端に体重計を置いて、体重を測る商売をしている人までいて。そんなの誰が払うの? と思ってしまうんですけど(笑)。法律ですべて管理するのは簡単かもしれないですけど、そこがある程度緩くても宗教が規律をもたらしてくれているから、その緩さがインドらしいんだと思うんです。
突拍子もない発想がビジネスチャンスにもつながると考えると、可能性に満ちた国だなと感じる一方で、14億人という人々がどのようなコミュニケーションをとっているのかが気になりますね。
笑顔までの距離。

コミュニケーションは全然違いますよ。日本だと、どうやって返事が返ってくるかなと想像しながら会話すると思うんですけど、インドでは “言葉を発した時点で、自分の責任はもうそこにはない” というようなことがよく言われますし。そんな感覚だからか、会話がそこら中に溢れていて、メトロの車内でもみんな会話しているので携帯を見ている人なんて誰もいないんですよ。もしインドにチャンネルを合わせるなら、まずは心を開くことからですね。
東京の人を見ていると、電車で携帯を見ていない人はいないと言っても大袈裟ではないかもしれませんが、何にしても面と向かったコミュニケーションが減っているからこそ閉ざしてしまっているような気がしますね。
インドから帰国してまず最初に感じたのは、日本って静かだなということでした。会話欲は現実の発声からデジタルの文字に置き変わり、SNSのタイムライン上に容量を積み上げるばかりですけど、脳にダイレクトに情報が入ってはくるものの、フィジカルなコミュニケーションはほとんどそこにはなくて、他人が介在する余地もない。でも、インドにはフィジカルな距離感がまだ残っているから、人と交われる土壌があるんですよね。インドのようにもっと予測不可能な日常を過ごすほうが案外楽しく過ごせるのかもしれないですし、会話があるほうが笑顔になれる瞬間もきっと多いわけじゃないですか。
距離を跨いだオーセンティシティ。

ゴアをアテンドしてくれた日本人女性は「食」の “アナログ” な部分に惹かれて飲食店をはじめたそうですが、加藤さんはどのようなところに魅力を感じていますか?
「食」の魅力は、単に空腹を満たすことや味覚を楽しむだけでなく、感覚を共有する手段になり得るところにあると思っています。例えば、高温多湿な気候の日本では、カビと共生することで独自の発酵文化が育まれ、それに伴って日本人の舌は「うま味」に敏感に反応するようになったという話を聞いたことがありますが、つまり、味覚は単なる生理的な感覚ではなく、土地の気候や文化的背景とも深く結びついているものなんですよね。そう考えると、料理における “オーセンティシティ” も、味の忠実な再現だけでは語れず、むしろ文化的な距離や差異があるからこそ、そこに解釈の余白や表現の幅が生まれると思うんです。で、その距離を埋めてくれるのが、今回のような旅での体験。器の質感、盛りつけのバランス、流れる音楽や現地での会話、そうした感覚の断片が料理に厚みを与えてくれるような気がするんです。
オーセンティックというと、 “ホンモノ” か “ニセモノ” の二元論で語られがちですが、料理の表現には寛容であるべきだし、その本質はもっと別のところにあるのかもしれません。
もちろん、文化的な背景を捻じ曲げてしまってはいけないんですけど、これだけ多様な文化や視点が同時に存在する東京のような場所にいると、自分が知っているはずの町にも知らない一面があったりしますよね。実は、帰国後もしばらくインドのSIMカードを入れたまま過ごしていたんですけど、携帯を開いたらヒンディー語のお店ばかり出てきて、同じ東京なのにまったく別の東京が存在していることに気づいたんです。SEO対策ではないですけど、実際に検索エンジンやアルゴリズムによって無意識に行動を促されている日常があるとしたら、デジタルって結構怖いなと思えてきて。

見えているようで、見えていない世界がある。そもそも、現代人は視覚に頼り過ぎなのかもしれないですね。
以前通っていた大学の講義の一環で検体解剖をしたことがあるんですけど、100年前の脳と現代人の脳を比較した際に、昔の人のほうは全体的にバランスがとれていたのに対して、現代人の脳は視覚野が異常に発達していたんです。だから、目で見たモノを信じる傾向が強くなってきているらしくて。ほら、広告でもシズル感で視覚的に訴求してくるじゃないですか。でも、見方を変えれば視覚以外の感覚をもっと開くこともできるはずで、目を瞑ることで広がる世界があるのかもしれない。なので、この店では現代の凝り固まった感覚を解きほぐすようなゴア料理を出していきたいと思っています。

Photos:Iori Kato
Words & Edit:Jun Kuramoto(WATARIGARASU)




