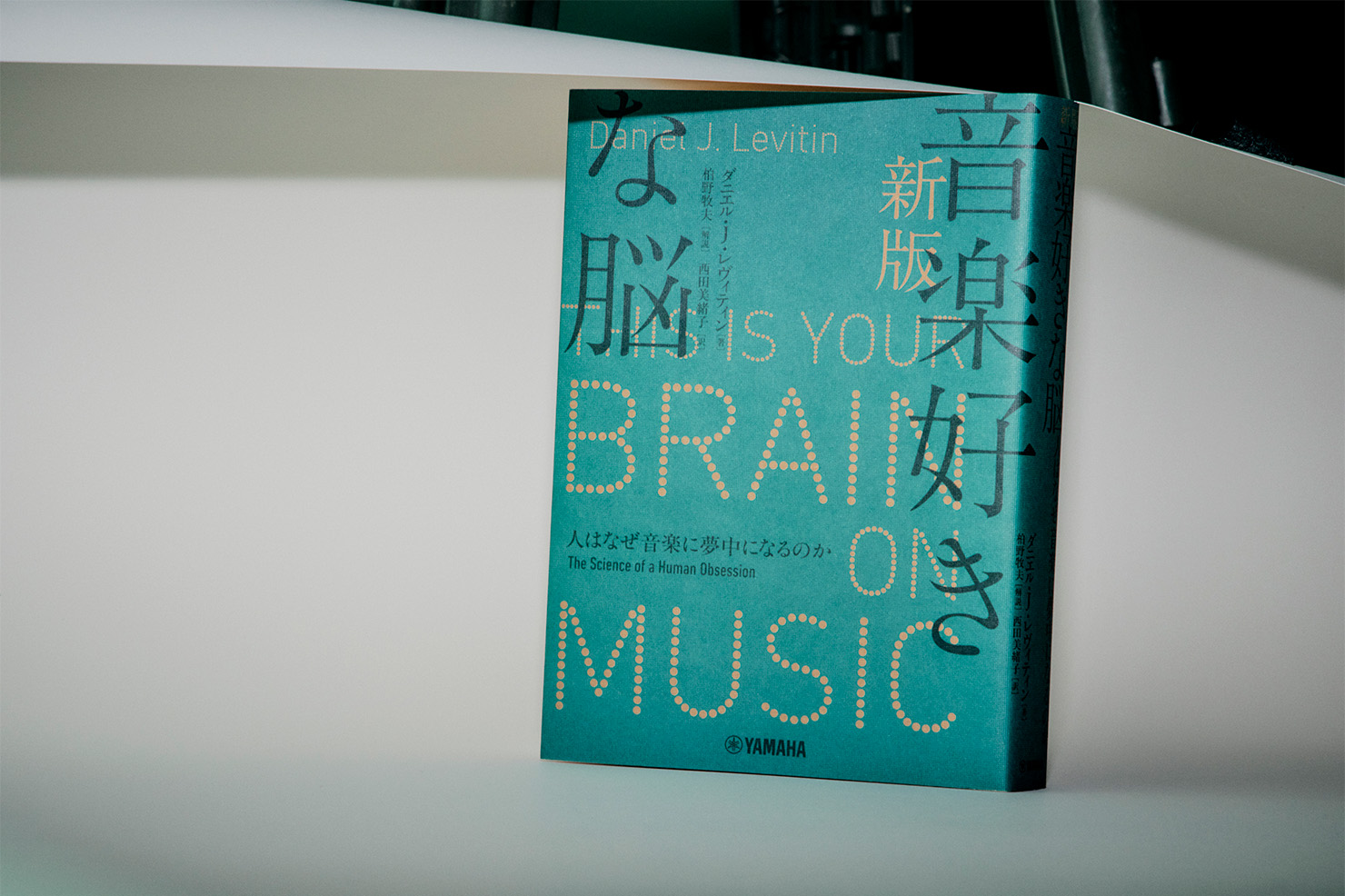「睡眠後進国」、日本はそう言われている。高度な文明をもっているのにも関わらず、いや、もち過ぎたからなのかもしれない。
2025年2月に誕生し、先日閉幕したイタリア・ミラノデザインウィーク2025に出展もされたプロトタイプ「ZZZN(ズズズン) SLEEP APPAREL SYSTEM」は、そんなレッテルをはがそうと試みる、衣服の形をした良質な仮眠、分眠に誘う斬新かつ画期的なシステムだ。「ZZZN」というプロジェクト自体は2023年に開催された “眠るための音楽イベント” からはじまったのだが、なぜ、のちに衣服(型のもの)へと辿り着いたのか。「ZZZN」の主導者であるNTT DXパートナー(NTT東日本グループ 以下、NTT DX)の尾形哲平と、クリエイティブディレクターを務めているKonelの宮田大に背景や意図を訊いた。
音/音楽には脳の全領域が使われる?
「脳はコンピュータにおけるCPU/ハード」「心はCPUによって実行されるプログラム/ソフト」と例えられたりする。人の脳は大まかに「計画や自制心に関わる」前頭葉、「聴覚や記憶に関わる」側頭葉、「運動や空間把握に関わる」頭頂葉、「視覚に関わる」後頭葉、そして「感情に関わる」小脳にわかれており、(一概に記すのは難しいのだが、簡単に言えば)何かしらの出来事に対して脳というハードの一部が働き、心というソフトと連携しあうことで行動や身体の反応が生まれている。とりわけ「それらの全領域、神経が総動員される」と言われているのが音/音楽だ。
(ちなみに以上の括弧をつけた箇所はダニエル・J・レヴィティン著の『音楽好きな脳 〜人はなぜ音楽に夢中になるのか』を参考にしている。)
あえてわかりやすい事例をもち出すと、誰かのライブを観て、大好きな曲が演奏された時に興奮し、鳥肌が立った経験があったりしないだろうか。こういったポジティブな現象が起きる理由として、ドーパミン(=脳への報酬)の影響がまず前置きに挙げられるが、実際はおそらくかなり複雑で、個人の思い入れなどの記憶をはじめ、様々な要素が絡みあって生じている。さらにはライブというシチュエーションにより、何の邪魔もない一点集中、逆の言い方をすれば、脳が大好きなものに包囲されているが故に、普段は起きづらいことが起きるのだと考えられる。
このような(日常生活では味わえないという意味で)少し特殊な音楽の視聴体験に関する良い側面はかねてから語られてきたのだが、近年、取り沙汰されるのはそれとは真逆、つまり「普段」や「副交感神経」、「α波(=リラックス時の脳波)」についてである。
いつの間にか「QOL」という言葉が広まり、私生活の質、パフォーマンスを上げようといった一種の “べき論” が謳われるようになって久しい。QOL向上の術は様々あるが、その中核のひとつと言えるのが睡眠改善だろう。サプリメント、食品、ドリンク、アイマスク、耳栓、枕やマットレスなどの寝具……枚挙にいとまがないこれら全体をまとめた国内市場規模は2023年時で1,800億円ほど、2030年には2,200億円弱まで伸びる可能性があると見込まれているそうだ。
様々な発想や成果に基づいた製品が生まれ続けている上に、瞑想アプリを含むいわゆるスリープテックツールもグローバルで発展してきており、幅が広がっている。ただ、耳栓のように物理的に音を遮断するものはあっても、反対に音で包み込むアプローチのものはなかったように思う。
以前、こちらの記事で睡眠やストレスに影響を与えているのは、街のところどころにある空調や車などの現代に欠かせない製品、それらによるわずかな音、振動なのではないか、といったことを紹介した。音によって本当に「脳の全領域、神経が総動員される」のであれば、寝ようとしているのに不快な音が意図せず鳴っている散漫な状態は、スリープさせたいコンピュータを処理させ続け、無意識的に負荷をかけている状態だとも言えなくない。ひいては振動も災いとなっているのであれば、耳栓では防げないかもしれない。ちなみに、だからこそ自然環境に身を置き、包まれることが人間にとって大事であるというのが前述の記事の結論だったのだが、事実だったとしても現実的ではないとも感じていた。
今回紹介するNTT DXとKonelによるプロジェクト「ZZZN」はこういった市場、状況にくさびを打とうとしているように筆者の目には映った。
音楽と睡眠の良質な関係。
「ZZZN」自体が誕生したのは2023年。後述する箱根の旅館でのイベントが現在に繋がる皮切りなのだが、そこに至るまでにも経緯がある。


尾形をはじめとするメンバーが20代後半から30代前半の追われる立場だった数年前、上からも下からも降ってくる様々なタスクを遂行するために、「とにかく自分自身のCPUの処理速度を上げる必要があった」と尾形は当時を振り返る。会社の課題と個人の課題の板挟みになっていた最中、並行してNTT DX社内で求められていた新たなイントレプレナーシップ(=社内起業)に関するリサーチで、尾形は仮眠の重要性に辿り着く。
尾形:ある時、仮眠をしっかり取れば、脳のパフォーマンスを最大化できるという内容が書かれた文献を読んだんですね。それをもとにまず提案したのが仮眠ボックスでした。そこが本当のスタートなわけなのですが、大雑把に振り返ると、社内で睡眠関連事業ができ、睡眠をスコアリングするためのサービスを作ったりしたものの、行動変容がなかなか生まれなかったんですよ。睡眠の状態を把握し、改善策を与えていくやり方だと、簡単に言うと楽しくない。目指さなければならなかったのは、何かをした結果の良眠。要するに逆のベクトルで考えなければならなかった。
そこで尾形が出会ったのが2022年にローンチされた、ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル(以下、ソニー・ミュージック)とKonelの共同制作による睡眠前専用プレイリスト「sasayaki lullaby」。その後、NTT DXは睡眠医学に基づく枕の開発などで知られるブレインスリープと共に、「sasayaki lullaby」を実証・検証する立場として参画する。NTTは途中段階からの参加のため、今回、「sasayaki lullaby」の詳細な狙いは語られなかったが、アプローチは「こういうものが良い睡眠に作用するだろう」というあくまで情緒的で感覚的なものだったそうだ。
その名が示す通り、「sasayaki lullaby」の楽曲は「ソニー・ミュージックの名曲・ヒット曲を子守唄のようにリアレンジカバー」したもの。当然、もとの楽曲のBPMはかなり抑えられており、リラックスできるよう仕立てられている。だがしかし、リラックスできる音楽イコール、インストゥルメンタルが通例だ。歌詞があっても落ち着けるのか、その点が「sasayaki lullaby」のチャレンジだった。
実証・検証の結果、リラックス状態の指標である副交感神経が優位になるなど、ポジティブな反応が見られたという。曖昧で確証が得られていなかった、音楽と睡眠の良質な関係。そこにさらなる輪をかけたのが、ポストクラシカルの雄である作曲家、マックス・リヒター(Max Richter)の傑作アルバム『SLEEP』の上演方法である。
オンラインと同時にオフラインを提供する責任。
およそ8時間の収録時間で構成された『SLEEP』の上演は晩から明け方まで、幕間も全くなく、睡眠のための演奏が続けられる。コンサート会場にはいくつものベッドが用意され、上演の合間、寝ることが許されている。「ZZZN」紹介の冒頭で挙げた「箱根の旅館でのイベント」は(晩から明け方までではなかったものの)このマックス・リヒターの方法に対するオマージュとして開催されたのだ。



ここでNTT DXはKonelと新たにタッグを組み、「ZZZN」という名を冠した、「音楽と睡眠」を包括的かつクリエイティブに考える持続的なプロジェクトが生まれる。封切りの箱根から2024年にはシンガーのCharaをメインアーティストに迎えたレーベル「SLEEP SOUND LABEL ZZZN」を発足(以下がそのプレイリスト)。睡眠をモチーフとした楽曲をまとめたEPを配信リリースし、それに関連したイベントも開催。同年、金沢21世紀美術館にてアーティストのJEMAPURが音響空間を構築し、三度のイベントを成功させた。
音楽とそれを補う光、寝具を伴う空間全体を使って、そこにいる人/寝ている人たちを包み込む。プロジェクトの軸が約2年の間でできあがったように思うのだが、次の2025年の一手がアパレルとは狐につままれるような感覚だった。以上の流れを汲めば、「次は居住空間などの環境構築なのでは?」と尋ねると尾形はこう答えた。

尾形:居住空間で言うと、例えばそこに住んでいる人の睡眠データ、サイクルに応じて電気が暗くなったり、香りが出たり、目覚めるタイミングでカーテンが開くといったことは他社さんのスマートホームでできるようになっているんですね。ではNTT DX、「ZZZN」の文脈に則ったアプローチは何か。これは宮田さんがおっしゃってくれたことなのですが、我々は通信の会社ではあるものの、現代はあまりにも情報が溢れ過ぎている。だからこそ、シャットダウンして皆さんを休ませてあげる必要がある、と。そのシャットダウン、仮眠や分眠をライフスタイルのなかでいつでも可能にするものは何かと考えて、行き着いたのが身につけるものでした。
宮田:現代って、24時間オンラインになってしまっているイメージがあるんですね。自分も然りなのですが、常にスマホを持ってチャットの返信をしたり、とにかくずっと何かをし、思考している感じがする。でも本来の睡眠は唯一、オフラインを確保できる時間のはず。NTT DXはオンラインを作る会社。だけれども、オンラインを作るということはオフラインを同時に提供する責任があるのではないか、と。それと、人は眩しかったらサングラスをかけ、暑かったら服を脱いだりしますよね。そういったふとした行動のように、寝たい時、フードをかぶることがあると思うんですけど、そこに睡眠に対してより効果があるものがあればと考えました。言い換えると、アパレルを作ったというよりも、スリープ機能がついたアパレルのシステムを作った感覚です。

この背景から誕生した、超大判のダウンコートのようなフォルムをもつ「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」。その特徴を、ふたりの話をもとにしながら触れてみよう。
人間本来の波長にあわせるということ。
宮田:フォルムに関して、纏う人に包み込まれる安心感を提供したかったという意図もあるんですが、モチーフにしたのは、明治期の日本に存在していた布団と寝巻きが一緒になっている夜着(よぎ)。それを発想源にしながら、裾や袖で温度調整ができるようになっていたり、作りが大きいので風も通せるし、逆に体温を逃したくない時は締めつけられるようになっている。

また今後、脳波を測定できる機能をつける予定で、フードにはそのための穴が予め設けられていたり、もちろん、フードをかぶると耳元からはニューロミュージック(=脳波の任意の帯域を増強・減衰するためにデザインされた音楽)が流れ、
そしてフードの目元には好みの色合いに変えることができる照明もついています。


内蔵されているニューロミュージックは深い睡眠に誘うものと、それよりもさらに深いもののふたつ。いずれもアーティストの小松千倫さんの作曲で音源には主にシンセサイザーが用いられていて、直接、脳波にニューロミュージックを届けることでα波が出やすくなっている。
尾形:これまでの睡眠データを活用した試みってスコアを出したり、アドバイスを促すといったことしかやっていなかったんですね。一方で「ZZZN」は当初、つまり箱根のイベントからそのデータを変換して、寝落ちしたら照明が消えたり、寝てる間に身体が動いたら照明も揺らぐなど、照明を使って睡眠データを可視化するということをしていた。「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」にも、そのアプローチは導入されていて、ストレス値に応じて光やニューロミュージックを出しわける仕掛けを組み込んでいます。

宮田:今回はヘルスケアデータをストレス値で取っていたんですが、今後、別の値も活かしながら機能を増幅させ、「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」自体に変化を与えていくことで、 “その人” によりフィットするニューロミュージックが生み出せるようになるかもしれません。
『SLEEP』の上演を追ったドキュメンタリー映画『SLEEP マックス・リヒターからの招待状』のなかに、マックス・リヒターと協働した脳科学者の話がある。
「 “8時間の曲を作る” なんて前代未聞だった。しかも “眠った状態のまま聴かせる” と言うんだ。マックスと最初に話したのは、繰り返しの音楽と睡眠の関係だった。人間の脳の中では860億個の神経細胞が個別に活動している。一方、睡眠中はそれらの細胞が集団で動く。だから睡眠中の脳波を測ると、緩やかな波が検出されるんだ。マックスが目指したのは、徐波睡眠(≒ノンレム睡眠)時の脳波とリズムが調和する音楽を作ることだ」

重要なのは、あれやこれやと装備をつけ足したり添加したりするのではなく、現代の忙しなさで乱れてしまう人間の本能的な部分を戻してあげること、そしてその一役を担うのが音/音楽なのかもしれない。カッティングエッジなプロダクトにも関わらず、「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」のモチーフが文明が進歩し過ぎる以前の日本人の知恵が生み出した夜着だったことも、どことなく人間回帰のシンクロニシティを感じさせる。
「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」はまだプロトタイプ段階ではあるが、睡眠後進国である日本における睡眠改善のオルタナティブになることを願う。
ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM

大阪・関西万博にも出展される「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」。プロジェクトチームは社会実装のための協業パートナーを募集しているとのこと。我こそは! という方はぜひとも下記HPよりお問い合わせを。
Photos(Product):Yusuke Maekawa
Words & Edit:Yusuke Osumi(WATARIGARASU)